トップページ > 報告・発行物 > 専門看護師・認定看護師活動推進委員会
-
バックナンバー
-
Vol.35
Vol.34
Vol.33
- 特別養護老人ホームにおける認知症ケアの課題―その人らしく生活するための多職種連携― (2025.09.07)
- 治療を受ける高齢者の身体的拘束による苦痛を減らし,生活の場へつなぐ急性期医療をめざして (2025.09.07)
Vol.32
Vol.31
Vol.30
Vol.29
Vol.28
Vol.27
Vol.26
- 「認知症の人と家族にとっての優しい街づくりを目指して」~訪問看護の現場から~ (2024.7.8)
- ”その人らしく最期まで生きる” を支える老健施設での活動~CureとCareの融合を地域連携・多職種協働で~ (2024.7.8)
Vol.25
Vol.24
Vol.23
Vol.22
- 急性期病院における特定行為研修を活用した認知症看護の実践 (2023.11.10)
- 「急性期病院で高齢者が安心して治療を受けられるために
~高齢者の意思を尊重したケアを多職種チームで実践する~ (2023.11.10)
Vol.21
Vol.20
- 認知症看護認定看護師としての視点の重要性について
-小さな気づきが認知症看護を考えるきっかけになる- (2023.7.11) - 高齢者の意思が尊重された日常生活が送れるように、看護師の困難と向き合う (2023.7.11)
Vol.19
Vol.18
- 精神科病院における認知症看護認定看護師としての実践報告
~院内の認知症看護対応力が向上した取り組みを振り返って~ (2023.3.1) - 専門看護師になって10年目~今できることを精一杯に~ (2023.3.1)
Vol.17
Vol.16
Vol.15
Vol.14
- 困ったときの拠り所となれる認知症看護認定看護師を目指して (2022.7.7)
- 今までの私、そしてこれからの私 -所属組織の統合再編 老人看護専門看護師としての新たな一歩を踏み出し- (2022.7.7)
Vol.13
Vol.12
- 本人、家族、皆で歩調をあわせて、横並びの関係づくり-地域包括支援センターでの活動報告- (2022.3.3)
- 地域の高齢者・家族が豊かに暮らし続けられるために-高齢者から学び、伴走する- (2022.3.3)
Vol.11
- 患者さんの“できること”を見極めるために必要なこと-患者さんとのコミュニケーションの推進- (2022.1.07)
- 高齢者の意思と過去の生活を踏まえた最期を見据えた支援-高齢者にとっての最善を目指して- (2022.1.07)
Vol.10
Vol.9
Vol.8
Vol.7
Vol.6
Vol.5
Vol.4
Vol.3
Vol.2
Vol.1
-
Vol.34-1認知症ケアをより良いものに―その先にある「笑顔」を目指して―
- 農協共済別府リハビリテーションセンター
認知症看護認定看護師
菅 真理 -
私が勤務する農協共済別府リハビリテーションセンターは,「すべての人が地域でしあわせに生活できる社会」を目指し,多職種が連携して活動しています.当院は,温泉地・別府市にあり,2023年時点で高齢化率は35.6%(全国平均29.1%)です.入院患者の約78%が65歳以上で,そのうち約10%が認知機能障害を抱えています.
私の認知症看護認定看護師(以下,DCN)としての活動は,2023年からで経験は浅いですが,認知症ケアをより良いものにしたいという思いを実現するために,職員や認知症専門医と協働し,認知症ケア加算1の算定体制を整えながら,日々のケア向上に取り組んでいます.
活動の一環として,認知症の人の身体拘束最小化・入院生活の質向上を目的とした,院内デイケアを提案しました.不定期ではありますが,農園芸・書道など患者さんの持てる力を活かすことができる内容で開催をしています.回想法は毎回実施しますが,参加者同士で記憶を補いあい,笑顔で話が弾みます.ある暑い日,日本茶と麦茶から飲み物を選択していただきました.「夏は麦茶」との声があがり,普段はあまり飲水しない方が自ら麦茶を選んで飲まれました.その姿から,患者さんにとっての『選択すること』の意味を職員一同で考えるきっかけとなりました.このように,患者さんの一言一句,日頃見せない生き生きとした表情・笑顔に私達は驚き,時に癒され,とても良い時間を共有させて頂き,ケアを提供する職員にも笑顔が増えたと感じています.
最後に,私のDCNとしての活動は始まったばかりですが,私達は活動を通して「その人」を知り,より個別性のあるケアを考えることができ始めています.これからも患者さんが自分らしく,尊厳を保ちながら入院生活を送ることができるように,また,認知症の人にとっての良いケアとは何かを模索しながら,時折見せてくれる私達へのご褒美のような「心からの笑顔」のために,一歩ずつ進んでいきたいと考えています. - 菅 真理(すが まり)
-
1992年:看護師免許取得
2004年:社会福祉法人 農協共済別府リハビリテーションセンター入職
2023年:認知症看護認定看護師
-
Vol.34-2根拠ある看護を求めてー老人看護専門看護師としての挑戦と連携―
- 2007年度認定 老人看護専門看護師
公益財団法人筑波メディカルセンター
田中 久美 -
当法人の看護部門の理念は,「私たちは真摯さと根拠のある判断のもとに,最善の看護を実践します」です.しかし,大学院へ進学する前,私は「根拠に基づいた看護実践とは何か」と自分に問い,答えが出せないまま,高齢者の「いつもと違う状態」に気づいていても,うまく周囲に伝えることができないもどかしさを抱えていました.そのような疑問と葛藤の中,老人看護専門看護師(CNS)を目指しました.大学院での学びを経て修了後は,急性期病院において高齢者が安心して入院生活を送り,適切な診療を受けられるように,組織のニーズに応えながら高齢者ケアの基盤づくりを目指して活動を続けています.
現場に戻った当初は,自身の専門性をどのように組織の中で活かせるかを模索しながらも,スタッフの困りごとに丁寧に対応する一方で,高齢者が持つ社会性を維持することや身体的不快の緩和を意識した支援を行ってきました.そうした取り組みを通じて,スタッフが「できた」と感じる経験を重ね,次の実践へとつなげる循環を育んできました.また,役割が重複する職種とは互いの専門性を尊重し,同じ事例を通してそれぞれの視点で話し合い,協働の基盤を築きました.教育面では,日常生活援助技術や看護倫理を学ぶ研修を企画し,看護の本質を見つめ直す機会を設けました.看護部長就任の年に始まったCOVID-19流行下においても,「身体拘束の最小化」を看護部のビジョンとして掲げ,プロジェクトを立ち上げました.そうした困難な状況下でも,高齢者の尊厳を守るケアの継続に尽力しました.
大学院進学前の問いに,今あらためて向き合うと,「急性期病院だからこそ高齢者ケアは重要である」と確信しています.そして,高齢者の様子に「いつもと何か違う」と感じたとき,身体的・精神的・社会的な特性に関する正しい知識をもとに,「何が起きているのか」をチーム全体で共有し,考えを深めることが大切です.そのうえで,経験から培った判断力や技術を生かし,高齢者にとって最善の診療やケアを提供していくというようなプロセスこそが根拠に基づいた看護実践だと考えます.そしてそれは,特別なことではなく,日々の臨床の中で「当たり前のことを丁寧に行う」姿勢から生まれるものだと思います.こうした実践を言語化し,他職種と協同しながら,根拠に基づく信頼性の高いケアを組織全体に広げていくことが,CNSの重要な役割だと感じています.
- 田中 久美(たなかくみ)
-
筑波メディカルセンター病院入職後、手術室、一般病棟、がんセンター病棟での勤務を経て看護師長となり、実践を重ねてきました。その後、大学院に進学し、2007年に老人看護専門看護師(CNS)の認定を取得。以降は横断的な立場で高齢者ケアを中心に活動し、2020年4月より看護部長、2021年4月より副院長兼務、2024年4月より看護部門長として勤務しています。
-
Vol.33-1特別養護老人ホームにおける認知症ケアの課題―その人らしく生活するための多職種連携―
- 特別養護老人ホーム明風園
生活支援グループ サブリーダー/2017年 認知症看護認定看護師
松村まり子 -
私は特別養護老人ホーム明風園(以下,特養)に配属になり,2017年に認知症看護認定看護師の認定を受けました.
特養は,要介護3以上で常に介護が必要な利用者が対象の施設です.看護職員配置が少なく,常勤の医師もいないため,
病院のような医療提供には限界がありますが,視点を変えて考えると,利用者の日々のQOL向上のために限られた医療資源を活用し,
生活機能の維持・向上に焦点をあてた看護やケアができると言えます.
Aさんは90代後半の女性で,要介護度5の認知症の利用者です.自宅では大家族に囲まれて生活し,ご自身の意向よりも家族の意向を尊重される方でした. 入所後は感染対策の観点から,発熱する度に他の利用者との生活から隔離され,ベッド上で過ごしました. Aさんは発熱時には,関節痛の症状と食事摂取量低下がありました.発熱の原因を探る採血では腫瘍マーカーが高値であることがわかりました. Aさんの意思は確認できませんでしたが,代弁者の家族に説明したところ,精査は身体の侵襲が大きいとの理由から希望はありませんでした. そこで,今後の対応について多職種カンファレンスを開催し,ADL低下予防とQOLの観点から定期的に解熱鎮痛剤を内服する方針を決定しました. その後,Aさんは解熱鎮痛剤使用により,時折微熱はありますが,他の利用者と一緒に食事や入浴など,人と触れ合う生活を送っています.
認知症の利用者は,ご自分の症状や状態を伝えることが難しくなり,更にマルチモビディティ(多疾患併存)のため症状が多様であることから, フィジカルアセスメントが重要です.その点で多職種協働は必須であり,特に介護職との協働が不可欠となり, 日頃より,お互いの保有している知識と技術を共有し,認め合う人間関係の構築が大切です. そのためには自ら多職種に対して真摯な態度,傾聴,声掛けなどを行い,意見交換がしやすい環境を作り,認知症の人が,その人らしく生活するための多職種連携をしていきたいと思います. - 松村 まり子(まつむら まりこ)
-
看護師免許取得後、総合病院に勤務
1998年 群馬県社会福祉法人 社会福祉事業団に入職 障害者施設を経て特別養護老人ホームへ異動
2017年 認知症看護認定看護師の認定を受ける 現在特別養護老人ホーム明風園にて勤務
-
Vol.33-2治療を受ける高齢者の身体的拘束による苦痛を減らし,生活の場へつなぐ急性期医療をめざして
- 川崎市立川崎病院
老人看護専門看護師
鳥海 幸恵 -
私が勤務する川崎市立川崎病院は,神奈川県川崎市南部医療圏の地域医療中核病院です.
私が老人看護専門看護師(以下,GCNS)として最も大切にしてきたことは,
状況の理解や変化への適応が難しい高齢者に生じる様々な心身の苦痛と混乱を極力減らし,
治療終了と同時に生活の場へ戻れるよう,心身の機能を維持するケアの普及です.
看護師経験4年目で,慢性期医療中心の系列病院から当院に異動した際,治療のための様々なデバイスを抜いてしまわないよう, やむなく身体的拘束が行われている多くの高齢患者さんを目の当たりにしました.どの様な看護技術や, 医師をはじめとした他職種とのコミュニケーションの技術があれば,身体的拘束を行わずにケアできるのだろうか. 高齢患者さんが少しでも早く身体的拘束を必要とする状態を脱するために,どの様な治療上の調整や意思決定支援が必要だろうか. もっと学んで急性期医療の場の高齢者ケアを変化させたい.それが,私がGCNSを目指した原点です.
大学院修了後,まず自部署で活動を開始しました.入院前の生活を踏まえた心身状態を丁寧にアセスメントし,「できること・強み」に注目すること. 状況理解を促すケア,自分でできることを増やすケアにより,身体的拘束を行わずにケアすること,少しずつ外していくこと. それらを実践で示し,ロールモデルとなるよう日々の業務を行っていきました. 認知症ケア委員会では,ケアの具体的場面を寸劇を通して提示し,多職種で治療・ケア計画を検討する研修会を実施するなど, 「身体的拘束をしないことによる生活機能を維持回復するケア」の普及を図ってきました.
現在は身体的拘束最小化委員会に所属し,認知症ケアチーム専従認定看護師とともに,代替ケアの普及に取り組んでいます. また臨床倫理コンサルタントとしても,身体的拘束を伴う治療が続くケースに関する,医療者のもやもやについて相談を受け, 少しでも早くその方が望む生活の場への復帰を実現する方策についての検討を支援しています. ご自身のことを代弁してくれる身寄りのない高齢者が多い地域でもあり,当院看護師がその方の代弁者として,最後の砦となる場面も多く経験します. 時間が限られる中でも対話を重ね,院内多職種・地域ケア従事者の皆さんと一緒にその方の最善を考えていくことにやりがいを感じています.
- 鳥海 幸恵(とりうみ ゆきえ)
-
大学卒業後、一般企業に就職.29歳で転職を決意.
2009年看護師免許取得.川崎市立井田病院・川崎病院勤務を経て2017年千葉大学大学院修了、老人看護専門看護師認定.以後、川崎市立川崎病院で活動中. -
Vol.32-1認知症の理解が進み,認知症の方も介護者も笑顔で過ごせる地域をめざして
- 公益社団法人広島県看護協会 訪問看護事業局 訪問看護事業部
認知症看護認定看護師
遠藤 泰子 -
私は,訪問看護師として働き始めた頃に独居の認知症の方で訪問看護の利用者Aさんから「あなたは私をわかってくれない」と言われ,
訪問をお断りされました.私は,Aさんに寄り添った看護ができているつもりだったため,驚き,傷つきました.
しかしこの経験が認知症看護認定看護師を目指すきっかけとなりました.
認定看護師になったのち認知症看護の経験を重ね,当時の私はAさんのニーズより,
自分のしてあげたい看護を優先し,Aさんの自尊心を傷つけたのだと理解するようになりました.
訪問看護の利用者は,認知症の診断がある人,ない人,様々で,介護者が認知症と診断されていることもあります.
私は,Aさんとの経験から,利用者や介護者の話を聞こうという気持ちで接するようになり,
徐々に認知症の方とのコミュニケーションが図れるようになりました.
今でも,私は認知症の方の対応に苦慮する職員からの相談時,訪問看護は利用者宅の訪問前から始まっている事, 前回と比較し環境が変化していないか情報を集めながらフィジカルアセスメントすること等を助言し, 必ず「利用者はどう言われていた?」と尋ね,利用者のニーズにあった看護は何かを考えてもらい,認知症の方の意思を尊重し, 私たちに伝えたいことは何かを想像しながら,その方に必要な看護を一緒に考えています.
今,私は地域の多職種や住民との活動の機会が増え,認知症カフェでの講義や若年性認知症カフェへの参加等を行っています. 若年性認知症の方は,高齢者が多い介護保険サービスは利用しづらく,地域に居場所がありません.これを解決するため昨年, 地域の多職種と若年性認知症カフェを立ち上げました.ここで参加者が「安心できる場所があり,うれしい」と話をされたり, 認知症の進行に対する不安を話した参加者に,介護経験者が体験談を伝える場面等があります. 認知症の方と支援者双方が喜びや哀しみを共有できる居場所作りに関わった経験は,私の財産です. 今後も,認知症の方を含めた地域住民が安心して在宅療養が続けられるよう,認知症の理解促進や地域の課題解決に向け活動したいと思います. - 遠藤 泰子(えんどう たいこ)
-
2004年 公益社団法人広島県看護協会 訪問看護ステーション「若草」入職
2018年 公益社団法人広島県看護協会 訪問看護ステーション「若草」所長
2020年 認知症看護認定看護師資格取得
2025年 公益社団法人広島県看護協会 訪問看護事業局 訪問看護事業部 部長
-
Vol.32-2高齢者の意思を大切にした医療・生活支援を目指して
- 医療法人財団神戸海星病院
老人看護専門看護師
正田 美紀 -
当院は,急性期一般病棟と地域包括ケア病棟を有する,地域に根差した病院です.私は,老人看護専門看護師として,
高齢者が自分らしい生活を継続できることを目指し,横断的に各部署と連携しながら活動しています.
高齢者のこれからの生活を支えるため,入院前の情報を活用し,その人らしさが発揮できるケアを患者・スタッフと共に検討し実践してきました.
また,退院前には,実践したケアを具体的に伝えることができるよう,看護サマリーの記載内容の改善と周知に取り組んできました.
そのほか,患者の視点に立った認知症ケア,生きる意欲につながる食支援,
高齢者とその家族がACPに取り組めるよう,医療者が支援する活動の普及に努めています.
これらの活動の背景には,私の介護付き有料老人ホーム勤務の経験が影響しています.家族には伝えられない「最期の時の意思」を 看護師に語る高齢者や,日々の生活の中で「意思」を示す認知症高齢者の方々に出会い,高齢者の「意思」を支えるため, 私たちケアスタッフは,個々の状況に応じ,ご本人やその家族と話し合い,生活の目標を明確にする様に努めました. これらのことは,治療やケアの選択において意思決定を支えることにつながり,様々な意思決定が求められる病院という場で, 医療者が,高齢患者の生活目標を含めた「意思」に着目し,ACPの支援をすることの重要性を改めて感じています.
当院は,通院患者や地域住民を対象とした勉強会を開催しています.私は,ACP実施が必要となる高齢者とその家族, そしてその他の世代の方々に対しても「意思を伝えること・知ること」の大切さが共有できる企画を継続していきたいと考えています.
現在は,認定看護師や関連委員会と連携し,医療・福祉従事者に対してACPの理解を深め,実践が定着するための体制整備に取り組んでいます. 将来的にはこれらの取り組みを病院全体へと展開し,組織的な体制の構築を目指しています.
- 正田 美紀(まさだ みき)
-
看護師免許取得後、一般病院、介護付き有料老人ホーム勤務を経て、2010年大学院修了
同年、神戸海星病院に就職。2011年老人看護専門看護師の認定を受ける -
Vol.31-1多職種連携を図り,本人の意思を尊重した退院調整を目指して
- 財団法人興和会 右田病院
2015年認定 認知症看護認定看護師
2022年認定 老人看護専門看護師
榎本 真紀 -
私は2015年に認知症看護認定看護師の認定を受け,認知症患者の離床を目的とし,回想法やアクテイビテイを行うことで,
入院生活を少しでも穏やかに過ごせるような環境作りを実践してきました.また,認知症高齢者が安心して居宅で暮らすことができ,
さらに高度な知識・技術を身につけて看護実践ができるように,2022年に老人看護専門看護師の認定を受け,
現在,右田病院地域連携室で退院支援・調整に従事しています.
認知症高齢者は,骨折や何らかの疾病の発症で身体的な苦痛を伴うことや,環境の変化に適応することが難しいとされています. また,さらなる認知機能の低下やせん妄,うつ状態からADLの低下に繋がり,自宅での療養生活が困難になってしまうことが多く, 入院時から早期に介入し在宅に戻れるよう支援,調整することが重要です.
私が日々の業務の中で大切にしていることは,本人や家族との関わりを通して,本人の意思,家族の意向を確認し, 病棟スタッフと①身体状況②心理状況③生活環境④社会・家族環境の側面から退院調整に向けて,多職種と情報共有をし, 話し合いをすることです.以下に,院内外の関係機関と密に連携を図り,自宅退院となった事例を紹介します.
アルツハイマー型認知症の既往がある80代女性のA氏は,食欲不振,リウマチによる体動困難のため入院されました. 入院時より安静臥床が長期化し,寝たきり状態となりましたが,「早く家に帰りたい」と苦悶表情が続いていました. しかし,家族は「日中夫婦二人だと心配.もう少し自分のことができればいいですが,今の状態では厳しいです.」 と難色を示されました.そこで,本人,家族,ケアマネジャー,病棟スタッフ,セラピストでカンファレンスを開催しました. カンファレンスでは,本人の思いを実現するために,介護保険の区分変更,リウマチ科のある訪問診療, 訪問看護やデイサービスの継続の提案をしました.また,家族の介護負担の軽減のため,訪問介護やレスパイト利用などの提案を行いました. A氏に対しては,在宅生活を見越した食事形態の変更やリハビリを実施したことで,当初自宅退院に難色を示された家族も, A氏の表情が明るくなっていくことを目の当たりにし,自宅退院の方向に理解を得ることができました. さらに退院まで「リハビリ頑張るんだよ」という家族の言葉が励みとなり,リハビリを継続することができました. また家族もカンファレンスの開催をきっかけに,A氏の在宅生活の具体的なイメージが安心につながり,A氏は自宅退院することができました. そして,退院時のA氏の笑顔は私にとって心の支えとなりました.
今後も本人の意思を尊重することや,地域との連携を継続していくことが私の課題であり,顔の見える地域の各連携会に参加しながら, 地域向けに認知症ケアに関する勉強会の開催や,院内外の多職種と連携を図り,本人の意思決定を支援し, 認知症高齢者が在宅に戻れるよう活動していきたいと考えます. - 榎本 真紀(えのもと まき)
-
2015年に認知症看護認定看護師の認定を受ける。
2022年に老人看護専門看護師の認定を受ける。
現在は、財団法人興和会 右田病院の地域入退院支援室所属
-
Vol.31-2高齢者が最期まで安心して生活できる地域を作りたい
- 伊勢崎市地域包括支援センター北・三郷
老人看護専門看護師
相場 健一 -
現在,私は保健師として地域包括支援センターに所属しています.地域包括支援センターの4つの役割(①総合相談支援,②権利擁護支援,③介護予防ケアマネジメント支援,④包括的・継続的ケアマネジメント支援)と保健師の役割を鑑みて,
1)地域に住まう高齢者の生活習慣病などの疾病予防とコントロールに努め健康寿命の延伸を目指す,2)認知症を有する高齢者の相談場所と居場所を提供する,3)地域住民ができるかぎり住み慣れた地域で住み続けられるよう支援することを目標にして活動しています.
具体的に上記記載の目標1)としては,地域に住む高齢者に対して公民館や住宅で行われるミニデイサービスや居場所に出向き,健康チェックと健康相談を実施し,かつ,自身が指導者資格を持つ貯筋運動を広め,フレイル予防に取り組んでいます. 2)としては,相談を受けている認知症高齢者に対してアセスメントを行い,家族に望ましい対応方法を伝えています.また,認知症カフェを①認知症の理解促進,②認知症高齢者への居場所の提供と家族支援,③地域住民やボランティアへの活動の場の提供を目的に毎月開催しています. 現在,認知症高齢者を含む25名前後の参加があり,ボランティアと協働し,懐かしい歌の歌唱,貯筋運動,レクリエーション,健康講話を行っています. 3)としては,1人暮らし高齢者を支援する「見守り訪問」を行い,身寄りのない高齢者と繋がりを作ることで早期介入や緊急対応に備えています.
今後の私が目指す活動では,今後の共生社会の実現に向けて,認知症高齢者の行動が「問題」と扱われるのではなく,「チャレンジ行動」と言われるように,地域住民の認知症に対する受け止め方が「新しい認知症観」としてポジティブに変わる必要があると考えており, 他の専門職らと協働して地域へ出向き,発信していきたいです.そして,ACPを普及することにより高齢者が自分の思いを実現できるよう活動していきたいと思います.
- 相場 健一(あいば けんいち)
-
2002年看護師保健師免許取得後、群馬大学医学部附属病院に入職
2009年群馬大学大学院へ進学し保健学修士を取得
2011年公益財団法人脳血管研究所介護老人保健施設アルボースへ入職
2016年老人看護専門看護師の認定を受ける
2022年同法人が市から委託を受けて運営している伊勢崎市地域包括支援センター北・三郷へ保健師として異動となる
-
Vol.30-1看護・介護の力で,「その人らしい暮らし」を最期まで支えるために
- 2015年認定 認知症看護認定看護師
2023年認定 老人看護専門看護師
中村 由喜子 -
私は,2015年に認知症看護認定看護師の認定を受け,急性期病院で約5年間,せん妄・認知症ケアチーム(以下,ケアチーム),院内デイケアの活動,リンクナースの育成,退院支援に携わってきました.ケアチーム活動では,週1回のラウンドを行い,治療に関する相談や,困難事例に対するケアをスタッフとともに実践してきました.
また,院内デイケアでは,認知症の方やせん妄を発症した患者様の生活リズムの改善を目的に活動してきました.日々の活動の中で,自分自身の知識やスキルの未熟さを痛感し,大学院に進学し,2023年に老人看護専門看護師の認定を受けました.現在は,住宅型有料老人ホームに所属し活動を続けています.
当施設では,高齢で認知症を患っている方も多く入居されています.私は日々,自分の意思が思うように表出することが難しくなる認知症の方の代弁者となり,本人の意思が尊重されるようご家族,スタッフと共有しながらケアを実践しています.以下,日々の活動について事例を通して報告したいと思います.
Aさんは,85歳の男性で膀胱癌の末期と診断されました.数年前にアルツハイマー型認知症と診断を受けており,独居で生活されていました.身寄りもなく,服薬の管理ができないこと,火の不始末でボヤ騒ぎがあり,自宅での生活が困難となり昨年入居となりました.入居当日から「自転車をとられちゃった」 と繰り返し施設内を歩き回っていました.スタッフから,Aさんが何度も同じことを言っては廊下を歩き回っており,目が離せないと相談を受けました.そこで,Aさんの行動の裏にある思いや,大切に思っていることを理解することが,Aさんらしさを取り戻し,穏やかに過ごせるケアにつながるのではないかと考え, 多職種カンファレンスの開催を提案し,Aさんの身体状況,心理状況,生活環境,社会・家族環境の4つの側面から話し合った結果,痛みのコントロールが不十分であることがわかり,鎮痛剤の使用方法の検討をしました.また,自転車はお世話になった社長に会いに行きたいという気持ちの表れであったことがわかり, Aさんに対するかかわりについて話し合いができました.現在,Aさんは,ADLや認知機能は徐々に低下してきているものの,疼痛コントロールを図りながら穏やかに暮らしています.今後も多職種でカンファレンスを行いながら,「その人らしさ」を考え,穏やかな日々が少しでも続くようにスタッフとともに考え,実践していきたいと考えています.
- 中村 由喜子(なかむら ゆきこ)
-
1998年看護師資格取得後、社会福祉法人恩賜財団栃木県済生会宇都宮病院に入職.整形外科、救急病棟、救急外来、退院支援課等を経て、2015年認知症看護認定看護師資格を取得し、せん妄・認知症ケアチームの専従看護師として約5年勤務し退職。
2023年に老人看護専門看護師資格を取得後、志摩市民病院で地域医療を学び、2023年6月Re HOPE浦和美園に入職し現在に至る。 -
Vol.30-2超高齢者の人生の最終段階を支える活動-臨床から教育に活動の場を移して-
-
群馬県立県民健康科学大学
老人看護専門看護師
戸谷 幸佳 -
私の老人看護専門看護師としてのキャリアは特別養護老人ホームから始まりました.開設されたばかりの施設で,看護スタッフも介護スタッフも施設での経験が少ない中,手探りでケアを行う日々でした.看取りケアに取り組んでいましたが,施設での看取りの経験が私自身や他のスタッフも少なかったため,施設で職員入居者,家族が安心して満足できる看取りケアに向けたくさんの課題に向き合いました.ある時,老衰で看取りケアを行っている入居者の体動が少なくなり,食事が食べられなくなっていく姿を見ているのが「こわい」と介護スタッフから相談された時がありました.言葉では訴えることのできない入居者が苦痛を感じているかどうか共にアセスメントする必要性を感じ,入居者の表情,動き,皮膚等の観察やケアを一緒に行い,今行っているケアは入居者の安楽につながっていることを確認しました.老衰により亡くなっていく高齢者の自然の経過を知り,変化を予測できることは,漠然とした看取りへの不安を軽減するのではないかと考え,勉強会やカンファレンスを行いました.
この施設での経験から高齢者が安楽に人生の最終段階を過ごすためには看護・介護スタッフが高齢者の苦痛症状を適切にアセスメント出来ることが重要であると考えるようになりました.それが,アセスメント能力を高めるための方策の検討,開発を行う現在の研究テーマにつながっています.
施設での活動では,経口摂取を続けたいと思う家族と入居者にとっては苦痛なのではないかと感じるスタッフとの思いの対立,最期を迎える場として施設を選択することへの家族の葛藤など倫理的な課題にも向き合あってきました.現在は大学で教員をしていますが,担当科目の一つに「看護倫理学」があります.学生が看護倫理について考え,倫理的感受性を育むことができるよう,自身の臨床での経験を授業で紹介するなど,これまでの活動を教育にもつなげています. - 戸谷 幸佳(とや さやか)
- 急性期病院にて血液・神経内科、循環器内科を経験し、大学院時代は訪問看護ステーションで経験を積む。社会福祉法人久仁会特別養護老人ホームくやはらで勤務し、2010年に老人看護専門看護師認定。2019年から現職。
-
Vol.29-1医療・ケアチームで行う認知症高齢者の透析療法選択にかかわる意思決定支援の実践
- 2015年認定 認知症看護認定看護師
東京慈恵会医科大学附属病院 看護部
赤間 美穂 -
当院は特定機能病院であり高度な医療を提供する役割を担う病院です.私は2015年に認定看護師の資格を取得し,2016年から認知症ケアチームの専任看護師として活動をしてきました.
その活動の中で認知症高齢者が透析療法を受けるときに身体拘束や薬物による鎮静をされている現状の多さを目の当たりにし,ご本人の意思に沿った透析療法選択の意思決定支援の必要性があると感じました.
認知症高齢者の治療選択にかかわる意思決定支援の際に,医療者がついやってしまいがちなのは認知症高齢者の意思はあまり聞こうとせず,家族と共に決めてしまうことです. ここに課題を感じたため,まずは認知症高齢者から意向を聞いてみようと行動しました.その意向とは透析をするかしないかではなく,本人の大事にしていること,今後どんな生活をしたいかなど, 毎日のようにベッドサイドに伺い雑談を通して,高齢者の人生の物語を聴きました.その話の中で,例えば「苦しくないように生きたい」というような言動があれば, 透析療法は体のゴミや余分な水を外に出すことによって苦しくなくなるなど,理解しやすいように説明を行いました.そして認知症高齢者の体調の良い時期を見計らって訪室し, ご自身の意向を話しやすい環境作りにも心掛けています.また,認知症高齢者から発信されるバーバルメッセージだけではなく,表情やしぐさ, 口調などのノンバーバルメッセージにも注目して本人の意思を推察することを大切にしています.
この実践は,ケアチームだけではなく医療チームとも協働して行っており,その実践がSDM(shared decision-making:共同意思決定)に繋がっていくと考えています. 意思決定支援においての看護師の役割は,まずは認知症高齢者を深く知ること,そしてその知り得た思いや考えを確認・代弁していくことだと考えています.
今後も認知症だから・・とあきらめてしまうかもしれない医療を認知症高齢者の意向に沿った医療が受けられるように支援していけたらと考えています. - 赤間 美穂(あかま みほ)
-
1995年 東京慈恵会医科大学付属柏病院就職
2001年 東京慈恵会医科大学附属病院へ移動
2015年 認知症看護認定看護師資格取得
2022年 東京慈恵会医科大学大学院 地域連携保健学 老年看護学 修士課程修了
現在、東京慈恵会医科大学附属病院 精神神経科病棟・外来 看護主任 認知症ケアチーム専任看護師として働く -
Vol.29-2精神科病院において高齢者理解やより良いケアの輪を広げる活動
-
2020年認定 老人看護専門看護師
山口県立こころの医療センター
光貞 美香 -
山口県立こころの医療センターは,精神科救急入院棟,精神科リハビリ・依存症治療等入院棟,認知症疾患医療センターなどを有し,県内精神科の拠点病院としての役割を担っています.
私は,2020年に老人看護専門看護師の認定を受け,精神科救急入院棟に所属しながら教育活動や研究支援なども行っています.
現在私が行っている主な活動としては,院内認知症カフェ(以下,オレンジカフェ)の運営と高齢者ミニ勉強会があります. オレンジカフェでは作業療法士,精神保健福祉士,公認心理士とともにプログラムを組んでおり,参加する高齢者に合わせて回想法,運動,調理,音楽,ものづくり,土いじりなどを取り入れ, 活動の中で高齢者の得意なことや持っている力を発揮していただけるような関わりを行うことで,高齢者の自尊心を高められるような関わりを意識しています. 高齢者の持っている力を病棟スタッフと共有すると「こんな一面もあるんですね」とスタッフの視点も広がるなど,活動の成果が見えてきたように感じ, 高齢者の背景・歴史をしっかり見つめていくことの大切さを実感しています.さらに,病棟だけでなく,今後の住み家でその力が活かされるために継続した関わりが行えるよう退院先の職員や地域の支援者への情報共有に努めています.
高齢者ミニ勉強会は,月に1回30分で職種関係なく自由参加としています.堅苦しくならないようわかりやすいテーマで講義と意見交換を行っており,徐々に参加者が増えてきました. ある日の勉強会では「メガネ・補聴器・入れ歯は大事だよ」をテーマにしました.これは,当院に入院される高齢者は精神症状や認知症の行動・心理症状により自傷他害や逸脱行為に至ってしまった方が多く, 混乱した状態で隔離環境への入院となる場合があります.隔離環境では安全確保のため必要最小限の物品しか持ち込むことができず,眼鏡や補聴器などが一時預かりとなることもあり, コミュニケーションを補うために必要な物が使用できず,高齢者にとっては生活しづらい環境だなと感じていました.そこで,どの程度のどのようなリスクがあるのかを再アセスメントし, できるだけ眼鏡や補聴器など身につけていたものは継続して使用できるよう働きかけ,感覚器からの情報を補うことの大切さを共有しました.これまで当たり前として行われていたことへ疑問を投げかけることで, 高齢者の生活環境を意図的に整えることへの意識が高まってきたと感じています.
これからも,自分にできることを地道に続けることで,高齢者の理解やより良いケアの輪が広がるよう仲間を増やしながら取り組んでいきたいと思います. - 光貞 美香(みつさだ みか)
-
看護師免許取得後,一般病院に勤務し,看護基礎教育に従事
2020年大学院修了後,山口県立こころの医療センターに入職し,老人看護専門看護師の認定を受ける -
Vol.28-1家で暮らしたい,を支えるための外来支援を目指して
- 2012年認定 認知症看護認定看護師
公益財団法人日産厚生会玉川病院
山﨑 美樹 -
私は認知症の方の「自宅に帰りたい」というご本人が望む場所に退院支援を行いたいと考え,2012年に認知症看護認定看護師の資格を取得しました.当時勤務していた回復期リハビリテーション病院では,病棟で回想法を実施したり,院内デイケアを立ち上げたりしました.また,地域包括支援センターと協働し,認知症予防教室などで地域の方と交流を深めながら,オレンジカフェ運営ボランティアも経験してきました.
現在は急性期病院に勤務し,認知症ケアチームを立ち上げて活動をしています.当院の認知症ケアチームは医師・看護師・薬剤師・社会福祉士・作業療法士が中心となり,認知症ケア委員会の中核メンバーの役割も担っています.
立ち上げ当初は認知症ケアチームの存在が院内に周知できず,病棟ラウンドに行っても「特に困っていません」と言われることのほうが多い状況で,薬物療法が中心でした.非薬物療法の重要性を浸透させるためにDCNが中心となって,リンクナースとともに病棟でリアリティオリエンテーションやコミュニケーション技術などのミニ勉強会などを繰り返し実施した結果,非薬物療法の重要性の理解と認知症ケアチームの活動が浸透していきました.現在は認知症ケア委員会のリンクナースに,各病棟の身体拘束率や認知症ケアチームラウンドの対象者のピックアップなどを任せています.そして認知症ケアチームはGCNSが中心となり活動しています.
私自身は認知症ケアチームで介入した患者さんの退院後の生活をフォローできるよう,外来支援のシステム作りに取り組み始めたところです.外来支援に力を入れたいと思ったのは,認知症ケアチームで介入し,家族との面談を行うことで施設入所から自宅退院になった患者さんを,外来で長期にわたってフォローした経験がきっかけでした.外来受診時にご本人と介護しているご家族の話を伺い,家の中で起こっている困りごとの解決方法をご家族と一緒に考えながら,ご本人が亡くなるまで数年にわたり支援しました.「自宅でみるのは大変だったけど,病院に来たら愚痴も言えるし,困ったことは一緒に考えてくれるし,連れて帰ってよかったです」と,最後にご家族に言われた言葉が今でも忘れられません.介護や医療のサービスを調整するだけではなく,ご本人と家族が来院された時に声をかけ,両者の話を聞いて,今困っていることを解決するにはどうしたらいいか一緒に模索することが,自宅での生活を継続するうえで重要だということに改めて気付かされました.認知症は他の疾患と違い,採血などの検査結果から病状の変化をアセスメントし,助言によってすぐに生活習慣が変化するなどの結果が出るものではありません.現在は他の分野の認定看護師から服薬管理や生活習慣の変化に対してどのようにアドバイスをしたらよいかと相談されたり,認知症ではないかと感じながら,どう介入したらいいのかわからないと他職種のスタッフから相談を受けるケースもあります.入退院を繰り返す患者さんのケースにおいては前回の認知症ケアチーム介入時の看護ケアが継続され,患者さん自身の困りごとが早期に問題解決できるよう外来から病棟まで,シームレスに認知症ケアが行われることが重要だと考えています.
- 山﨑 美樹(やまさき みき)
-
2012年 認知症看護認定看護師取得
2018年 公益財団法人日産厚生会玉川病院に勤務
-
Vol.28-2老人看護専門看護師認定からの4年間の活動を振り返って
- 2020年認定 老人看護専門看護師
筑波メディカルセンター病院
石井 智恵理 -
当法人は1985年のつくば科学万博の開催時に設立され,地域医療支援病院として救命救急センター及び茨城県地域がんセンターを擁する高度急性期医療を担っています.
2020年に老人看護専門看護師(以下GCNS)認定を受けた私の活動は,新型コロナウイルス感染症の波と共にスタートしました.コロナ専門病棟に配属当初は,厳重な感染対策下であり,経過の見通しや隔離環境への不安を抱く様々な年代の患者に対応していました.うなずきや身振り,目で笑顔を作ること等で共感を示し,温かさが伝わる関わりを大切にしながら身体管理を行ったことは,高齢者看護の実践そのものであり,看護の基本だと強く実感しました.
認定当初は自分を不甲斐なく思う気持ちが大きくありました.しかし,「自分らしく看護の基本に忠実に高齢者看護を実践していこう!」との思いを胸に,認知症ケアチームの活動を基盤に各病棟へ足を運びました.認知症高齢者の手術では術後に合わせて訪問し,せん妄患者には夕方に再度訪問する等相談しやすい環境を意識しました.ケアの拒否が強い認知症高齢者では,スタッフの話に傾聴しつつ,「この方はこんなことに困っていたのでは?」「この身体的状態ではきっと苦しいよね」と,高齢者自身の困り事や行動の背景に目を向け,高齢者の不安や苦痛をスタッフと一緒に捉えなおし,関わり方を見せて実践を示していきました.認知症高齢者やスタッフの関わりの変化は逃さずポジティブフィードバックし,スタッフの成功体験につなげていきました.高齢者の身体的・精神的苦痛に対処していくことが大切であることを地道に示してきた日々の活動により,GCNSとして信頼され,相談が増えていきました.2023年度からは身体拘束最小化プロジェクトチームのリーダーを任されています.また,身体拘束の対象になりやすい認知症高齢者の理解やせん妄対応,看護倫理の研修を開催し,各委員会や病棟に出向き,高齢者の尊厳を守るため,身体拘束最小化の考え方や対応等を周知したことにより.それにより,外来や小児病棟,在宅部門からも一緒に考えていきたいと声をかけられるようになりました.活動はセラピストや介護士との組織的な取り組みの輪にも広がっています.
身だしなみを自然に整える等の日常ケアや,高齢者の尊厳を守りながら治療する環境提供を大切にし,多職種で配慮できる組織作りの一部を担えるよう,今後も精進していきたいです.
- 石井 智恵理(いしい ちえり)
-
看護師免許取得後、北里大学病院に入職
2005年 カナダへ語学留学
2007年~筑波メディカルセンター病院に勤務
2020年 老人看護専門看護師認定 -
Vol.27-1介護老人保健施設における認知症看護認定看護師の活動と課題
- 2012年認定 認知症看護認定看護師
医療法人社団静和会 介護老人保健施設 エル・クォール平和
泉 玄太 -
私は認知症になっても「その人らしさ」が失われず,生活の場が変わっても「これまでの暮らしが継続」されるように支援できる看護師になりたいと考え,
2012年に認知症看護認定看護師の資格を取得しました.
現在は,在宅支援・在宅復帰のための地域拠点となる介護老人保健施設に所属しています.所属施設での認知症看護認定看護師の活動を紹介します.
1.その人らしさを大切にした多職種におけるチームケア
私の所属するチームは,医師・看護師・介護福祉士・介護相談員・リハビリ関係職等の多職種で構成されています. 当施設では,利用者の方のこれまでの暮らしが記載された情報シート=「暮らしの様子シート」を活用しています. このシートには,「好み」(嗜好品・馴染みの物・お洒落・色の好み・食べ物の好き嫌い),「生活」(食事環境・就寝時間,利き手や整容面の生活習慣・得意・苦手なこと), 職歴や暮らしていた土地,暮らしの年表などが記載されています.暮らしていた土地のことや職歴を話題にしながら会話に花を咲かせ, 整容場面では使い慣れた化粧品や衛生用品を用い,朝にコーヒーを飲む習慣へ配慮するなど,生活に寄り添ったケアを展開するために活用しています. 慣れない環境下で生活を円滑に営むことが難しくなった場合において,尊厳を尊重した基本的ケアに立ち返り,利用者の方の困り事をご本人の言葉にし, 困り事の背景や,もてる力を活かせるケアをスタッフと共に整理し,ケアの根拠を提示しながら,チーム全体で展開できるようなアプローチを心がけています.
2.認知症ケア向上委員会の活動
認知症ケアにおける,多職種でのチーム力の底上げを目的に活動しています.本年は,暮らしがより豊かなものとなるよう非薬物療法の充実を目標としています. 昔の遊びや暮らしをテーマに写真などのアイテムを用いた回想法,リラクゼーションを目的としたタクティールケアに準じた手のマッサージケア, 七夕の短冊や年賀状の作成を通じて想いや願いを表出することでメンタルヘルスを高めることを目的とした筆記開示を計画的に実施しています. また,「活き生きプログラム」と題し,もともと晩酌を楽しみにされていた方とのノンアルコール宴会など生活背景を考慮した楽しみを継続的に提供できるように計画しています.
3.課題と今後に向けて
介護老人保健施設は多様な機能を持ちますが,主に在宅支援としての役割があり,在宅へ向けた調整や連携が必須となります. 施設から生活の場を移す場合においても,切れ目のないケアを受けることができるよう,認知症看護認定看護師として,概念化力や先見性を磨くことが,今後の課題と捉えています. また,利用者の方が笑顔で過ごすことができるように,もてる力の可能性を信じることを止めず,安心や心地良さを感じて頂けるようなケアをチーム全体で取り組めるように精進していきたいと考えています. - 泉 玄太(いずみ げんた)
-
看護師免許取得後,一般病院に入職
2012年に認知症看護認定看護師認定
2016年より介護老人保健施設 エル・クォール平和入職 -
Vol.27-2高齢者が望む暮らしを実現できる地域を目指して
- 2019年認定 老人看護専門看護師
有限会社相模テクノグループホームあかつき取締役訪問部長
訪問看護ステーション所長
田島 玲子 -
当社は,人口3万人あまりの山間部の町に,“認知症があっても,住み慣れた地域で最期まで自分らしく過ごしていただく”ことを目指し,1999年に認知症グループホームを開設しました.
私は,“最期まで施設で過ごしてほしい”という熱い思いの経営者から請われ,2002年に訪問看護ステーション所長に,就任しました.
その後,小規模多機能型居宅介護や認知症デイサービス,サービス付き高齢者住宅,定期巡回随時対応訪問介護看護などの地域に密着した事業を展開しています.
現在は,多疾患併存状態にある認知症高齢者の健康管理を主な役割としながら,ご本人の“望む暮らしの実現”に向けて,生活の場や支援内容を“オーダーメイドのケア”が提供できるようにサービスの調整を図っています. 同時に,訪問看護ステーションの所長として,地域で活動している関係者との連携を図りながら,地域住民への支援も続けています. また,老人看護専門看護師の認定を受けた2019年に,“人生の最終段階における医療・ケアの意思決定プロセスに関するガイドライン”の改定があり, 自施設である“グループホームを中心とした地域包括ケアシステム”の推進が目指すケアの実現に繋がると考え,“出張!あかつき まちの保健室”事業を開始しました. しかし,新型コロナウイルス感染症の蔓延があり,事業は頓挫しています.
認定を受けて5年が経過しました.これまでの学習成果は,見えていなかった利用者の背景や地域の資源について,視野が広がったことです. アセスメントの深まりや広がり,病態と生活の関連図作成が楽しくてたまりません.まだまだ利用者のケアを通して多くを学ばせていただく毎日です. 自身は60歳と還暦を迎えるに至りましたが,“人生100年”,高齢者看護の高みを目指して,これまでに支えてくださっている諸先輩方とのネットワークを駆使して,活動を続けていけたらと思っています.
田舎町では,若い後継者となる人材がなかなか集まらない現状があります.高齢者看護の楽しさや喜びを若い方たちへも知っていただけるように,実習の受け入れや研究協力にももっと力を入れていきたいです. - 田島 玲子(たじま れいこ)
-
看護師免許取得後,一般病院や看護基礎教育に従事
2002年に,グループホームあかつき入職。2015年から現職
2019年に,老人看護専門看護師認定
-
Vol.26-1「認知症の人と家族にとっての優しい街づくりを目指して」~訪問看護の現場から~
- 2017年認定 認知症看護認定看護師
おかもと訪問看護ステーション垂水
信川 千賀子 -
私は,「もっと早い予防の段階から介入し,軽度の認知症の人(以後本人と略す)を取り巻く人的環境を多職種チームで整えたい」と考え,ケアの現場を病院から在宅へと移行したのが7年前です.
現在は,訪問看護ステーションに在籍しています.
在宅では認知症と気づかずに様々な苦悩を抱えながら日常生活を送っている本人と家族が暮らしています.ごみ屋敷となり近所から相談が上がってくるケース,警察やスーパーで保護されるケースもあります. 重度認知症,独居のガン末期のケース,事故を繰りかえすが免許を返納できないでいるケース,ギャンブル依存で娘の大学資金も全て使ってしまったケースもありました. また,認知症とわかっていても家族は受容できず他者にも話せず自分達でなんとかしようと疲弊してしまう…負のスパイラルが回り始めると,病気であることも家族であることも遠のき, やがて虐待につながってしまうケースもありました.家族が目の前の現象は本人の心の声と捉え,その奥にあるものは何かを考えられる,まだゆとりのある段階から関わりサポートする必要がありました.
現在の私の活動は以下5点です.
① 本人に困りごとが出現したときには多職種チームで丁寧に紐解いていく作業を行い本人が持つ強みを活かしたポジティブパーソンワークを展開していくこと
② 本人と家族の困りごと,症例と関わり,成功体験を外部に伝えていくこと
③ 地域の医療介護サポートセンターで〈医師会・薬剤師会・歯科医師会・ケアマネ会・訪問看護・ヘルパーステーション対象〉認知症看護の現状と成功体験を伝え協力者の輪を拡大すること
④ 協力者の内発的な動機付けを行うこと
⑤ 地域の茶話会や,民生委員,老人会などで「認知症と物忘れとの違い」「認知症予防について」を説明し事例を通して認知症の人への声がけが自然な形で行えるようになること
⑥ 元気な時期から自分史をメモすることを勧めること
たくさんの人の研ぎ澄まされた感性で認知症の人の瞬時の輝きを捉えていけるチーム力とケア力は,まさに認知症の人にエネルギーを逆に頂いている瞬間だと感じています. これからも認知症の人の理解者を増やし本人と家族にとって優しい地域を目指したいと思います.最後に私がいつも前を向いて認知症ケアについて考え実践できるのは,大切な仲間がいるからこそと感謝しています. - 信川 千賀子(のぶかわ ちかこ)
-
2001年 認知症疾患(旧 痴ほう疾患)専門病院看護師長として就任.
2004年 認知症研究研修センターで認知症介護指導者研修に参加.他職種と共に認知症ケアを学ぶ中,自身の認知症看護の視野の狭さを痛感する. その後,神戸市認知症介護指導者として認知症介護実践者研修・リーダー研修の企画・運営・講師を務める.
2011年 認知症ケア上級専門士取得
2017年 認知症看護認定看護師取得
2019年 おかもと訪問看護ステーション垂水管理者に就任.
-
Vol.26-2”その人らしく最期まで生きる” を支える老健施設での活動~CureとCareの融合を地域連携・多職種協働で~
- 2017年認定 老人看護専門看護師
社会福祉法人栄和会 介護老人保健施設あつべつ
中川 真奈美 -
北海道の中核,札幌市にある「あつべつ」は近隣や道内の医療施設・在宅支援機関と連携し,超強化型老健として高齢者の生活を入所・通所・訪問の3本柱で支援しています.
初動からゴールを見据え,在宅復帰から看取りまで幅広いニーズに対応するよう多職種を巻き込み,専門性を引き出す調整役が重要な責務と考え活動しています.
がん拠点病院で勤務する中,つらい治療に身を置く多くの高齢者と出会い,次第に高齢者が疾患や障がいを抱えていても,共存しながらエンドオブライフを豊かに生きるための看護を目指したいと思うようになりました. 治療にのみ特化するのではなく,生活者としてその人らしさに視点を当てたCure(疾患治療) とCare(生活の質を高める支援)の融合を目指し,自法人での活動が20年を迎え感慨深く思います.
「あつべつ」は100床中,認知症専門棟50床を有し,認知症自立度Ⅲ以上73%とその割合は年々増加しています.認知症疾患,慢性心不全,慢性腎臓病,がん疾患を抱える方,100歳を超える方の支援が増えており, QOLと尊厳を大事に過不足のない適切なCureと個別Careの重要性を痛感しています.そして,高齢者との関わりから感じ取る微細な反応を多職種で共有し,大切に繋いでいくことを大事にしています. 日々の生活支援を通して,多職種の倫理的感受性が高まるよう「気づき(倫理的課題)」を動機付けし,多職種が共に考え意見を交わし,解決までのプロセスを大事に支援しています. 実践の成果をフィードバックすることで自信となり,協働意欲の向上に繋がっています.
感染症や骨折等の急性疾患,基礎疾患の重度化から,ACPにより医療施設でのCureを選択する場合は,治療目標を医療施設と十分に相談します. 入院が長期化しないよう受け入れ体制を多職種で整えることで,老健の場での継続的なCure と連続性のあるCareが可能になると実感しています. また,高齢者個々の状態像に応じ,看取りまでの日々丁寧な支援は「あつべつ」の強みと確信しています.
今後も,“その人らしく最期まで生きる”を支えるチームの一員として,地域連携・多職種協働の充実を目指し,老健の場からGCNSとして研鑽を重ねていきたいと思います. - 中川 真奈美(なかがわ まなみ)
-
北海道がんセンターに勤務し,看護管理経験の後2003年社会福祉法人栄和会入職.介護老人保健施設あつべつで高齢者看護に従事し,地域包括支援センター開設にも参画.2017年老人看護専門看護師取得,2020年より副施設長.
札幌医科大学,北海道医療大学臨床教授.看護大学・大学院,福祉専門学校,高齢者介護施設,一般市民対象の高齢者ケア,認知症ケアの講師としても活動している. -
Vol.25-1診療所において住み慣れた地域での暮らしを支える~医療とケアの両面の支援~
- 2019年認定 認知症看護認定看護師
ろっこう医療生活協同組合 うはらクリニック
高野 幸子 - 私は,在宅療養支援診療所として認可を受けたクリニックに勤務しています.平日の午前は外来診療,午後から訪問診療をおこない,夜間・土日祝日の高齢者の体調不良時は,臨時往診やクリニックからの訪問看護によって,早期に医療・看護ケアを提供し,ご自宅での療養生活を支えています.
- 地域には,脳血管疾患・糖尿病・高血圧・COPD・心不全,神経難病,がん患者など様々な疾患を抱えた方が暮らしており,これらの疾患治療中に認知症に罹患される方やすでに罹患されている方もいつもと変わらない生活を送られています.その様な現状の中で,生活機能が低下する認知症の方の地域での生活を支える看護を提供したいと思い,認知症専門医が所属するクリニックでの勤務を教育課程修了後に選択しました.
- 専門医を訪ねてくる認知症を患った方・ご家族様の相談受診は増えています.特に中等度の認知症の方は,記憶障害も進み,生活機能障害も現れ,できなくなることに対しての不安や恐怖・孤独感を抱きやすくなります.家族介護者は,介護負担が増え,ストレスを抱え込みやすい時期でもあります.そこで,Zarit介護負担尺度を利用し,家族介護のストレスを把握し,認知症教室という形で家族へのアプローチを行いました.本人の行動に困っていたり,将来の不安があると回答する家族が多く,病気や症状の理解だけでなく,実際の介護に有用な介護方法や関わり方,認知症の経過について具体的に伝えていく必要があると思いました.また,同じ悩みを抱えている家族介護者の交流は,お互いの介護を振り返り,認め合えたり,新たな介護方法を見出せたりして,終了後はみなさんの笑顔を見ることができるので,この様な教室を定期的に開催していきたいと思います.
- 在宅の現場では,医療・介護・福祉職以外に地域住民を含め,民生委員など様々な方と関わる機会も多く,それぞれの視点から得た些細な情報は,認知症の方の生活継続を考える重要な情報となります.今後も,認知症の方の思いに寄り添いながら,五感を働かせつつ,事実をありのままに情報収集して,根拠をもったアセスメントをおこなうことで,住み慣れた地域でその人らしい暮らしを支えていきたいと思います.
- 高野 幸子(たかの さちこ)
- 病院・訪問看護ステーションを経て、2018年より現職。2019年認知症看護認定看護師の認定を受ける。
-
Vol.25-2「その方の人生」に皆が目を向け、最善の医療が提供できる急性期病院を目指したい
- 2015年認定 老人看護専門看護師
長崎大学病院
井手 みのり - 私は,看護師免許取得後,急性期病院一筋で働いてきました.現在勤務する長崎大学病院は,病床数874床,長崎県の高度急性期医療を担う病院として,毎月1,500名超の患者さんが入院し,短い在院日数で治療後,次の療養の場に移っていきます.入院患者の約半数を高齢者が占め,身寄りのない方や老老世帯,高齢化率40%を超す医療過疎地で暮らす方も数多くいます.
- 急性期医療の現場では,侵襲的治療や急変時の延命選択など,人生を左右する意思決定を迫るにも関わらず,医療者が意識的に問いかけなければ,その方が入院前にどのような生活をしていたか,何を大切に生きてきたのか知らないまま,治療方針の決定がなされることも少なくありません.私の役割は,患者さんの生活に携わる全員が,目の前の状況だけでなく,その方の生き方に想いを馳せながら,患者さんにとって最善の選択ができるよう支援していくことだと考えています.
- 例えば,認知症ケアチームラウンドで,私は「何の仕事をしていたか」「好きなことは何か」等の質問をし,患者さんを知ることに時間を使います.意思疎通が困難な患者さんには,音楽,写真や絵など,五感を使ってその方が反応を示してくれる何かを見つけようと試みます.今まで不安そうだった方や無表情だった方が,自分について語ってくれた時,笑顔を見せてくれた時,その方の人生の一部を共有できたような喜びを感じます.うまくいくことばかりではありませんが,関心を持つ姿勢が重要と考えています.患者さんに関心を持つことで,徐々に病棟スタッフにも変化が出てきました.以前は,「患者さんがどうやったら落ち着いてくれるのか」と問題行動への対処を知りたがるスタッフがほとんどでしたが,ここ数年,チームが介入する前から「患者さんはどうして帰りたいんだろう.何に困っているのかな」と,患者さんの思いや体験に寄り添う発言や対応が増えています.職種を超えて,この変化を少しずつ増やしていくことが,高齢者ケアの質向上とともに,急性期病院で働く医療スタッフのやりがいにもつながっていくと感じています.
- 〈看護はサイエンスでありアートである〉というナイチンゲールの言葉は,私の心の支えです.科学的根拠に基づいた実践は大前提として,看護の醍醐味はやはり,目の前の高齢者をもっと知り,心を通わせるため,想像力を働かせて感性を磨いていくことだと信じて,これからも老人看護専門看護師として自己研鑽していきたいと思います.
- 井手 みのり(いで みのり)
- 都内急性期病院の循環器内科外科・呼吸器内科外科・皮膚科病棟で勤務する中、せん妄や退院困難な高齢患者の対応、多職種協働の難しさに悩み、看護師10年目で大学院進学を決意。 2012年修士課程修了後、長崎県へ移住。現職に就き2015年老人看護専門看護師の認定を受ける。外来、病棟、地域医療連携センター勤務を経て、現在は認知症ケアチームの専任看護師として活動している。
-
Vol.24-1住み慣れた地域で最善のケアにつなぐ ~多職種との協働を通して~
- 2013年認定 認知症看護認定看護師
一般財団法人 神戸在宅医療・介護推進財団 認知症対策課
認知症初期集中支援チーム コーディネーター
久保田真美 - 私は、一般財団法人 神戸医療介護推進財団に所属し、神戸市からの委託事業である認知症初期集中支援チーム(以下、チームとします)で活動しています。
- チームは、認知症サポート医、保健師や看護師、作業療法士、社会福祉士、精神保健福祉士等の医療系福祉系の専門職で構成されています。対象者は、認知症の疑いがあり、生活に支障をきたしている方や、家族や医療・介護サービスを提供する支援者が対応に苦慮している認知症の方です。主に、地域包括支援センター等からの相談を受け、情報を整理した後、チーム員2名で対象者や家族のもとを訪問してアセスメントをします。その後、チーム員会議を開催して、関係機関やチーム員とともに支援の方向性を定めます。対象者の意思が尊重され、住み慣れた地域で生活が継続できるように、適切な医療や介護サービスにつなぎ、概ね6か月でチームの介入は終了になります。
- 昨今、身寄りのない独居の高齢者や老老世帯の増加、キーパーソンがなんらかの疾患を抱えているケース、経済的困窮に直面しているケース、ゴミが山積みで悪臭が漂うケースなど、抱えている問題が複合化、深刻化してきています。誰もが助けや支援を求めているわけではなく、「人の世話にはなりたくない。放っておいてほしい。」と病院の受診や支援の導入を拒否されることも珍しくはありません。本人の視点に立ち、これまでの生活歴や環境から本人の思いを考え、訪問を重ねるなかで関係性を築き、最善な生活や支援を本人や家族とともに考え、医療や介護サービスにつなげていきます。しかし、やっと打ち解けてくれた矢先に不慮の事故で亡くなった方や、救済のために入院したはずが病院でベッドから転落して骨折したのを機に自宅に帰れなくなった方もおられました。そのような時は、後悔や無力感に苛まれますが、仲間と共に振り返りを行い、再度前を向いていけるように努めています。
- 地域で多職種と活動していると、認知症ケア経験や地域での活動が数十年のプロフェッショナルな支援者や、人生経験豊かで超越的な人間力を有している支援者に出会います。時に劣等感でいっぱいになり、「認知症看護認定看護師」の肩書を重く感じることもありますが、人との出会いに感謝しながら、自己研鑽に努めたいと思っています。
- 久保田 真美(くぼた まみ)
- 病院、訪問看護ステーション、若年性認知症支援センターを経て、2023年度より現職。2013年に認知症看護認定看護師の認定を受ける。
-
Vol.24-2患者さんがより自分らしく過ごすための多職種チームの活動
- 2012年認定 老人看護専門看護師
国立病院機構七尾病院
田本奈津恵 - 令和6年1月1日M7.6の激しい揺れ、家屋の倒壊、地盤の隆起、大津波警報、一瞬にしてのどかな田園風景を激変させた能登半島地震が発生し、仕事初めは、被災患者さんの受け入れから始まりました。まだ日常を送れない日々ですが、「能登はやさしや土までも」の言葉のようにお互いに助け合い、声をかけ合いながら過ごしています。七尾病院は、政策医療を担う病院で「笑顔と誠実な医療を通じて世の中に貢献する」を理念とし、主に神経難病や慢性疾患、重症心身障害者の方が入院され、大半の方が高齢者です。みどり豊かな能登島や波穏やかな七尾湾、和倉温泉街が取り戻せるよう頑張っています。
- 私は、認知症ケアや退院支援、看護研究活動など病棟スタッフと共に取り組んでいます。認知症ケアでは、転倒転落防止や食事摂取量の低下、無気力、せん妄などの相談が多くあり、 多職種チームで行う院内デイケア「ほほえみサロン」を実施しています。認知症予防と対応についてのプログラムを週1回行い、体操や呼吸法、カラオケ、園芸療法に着目し生活の質向上に努めています。震災で被災された患者さんが避難所、病院と住まいを移す中で、新聞を読む、好きなコーヒーを飲む日常を取り戻せたこともありました。また、なかでも生け花は、病院周囲や職員の自宅庭に咲いている花を使い、色や香り、葉や枝、冷たい水等に触れることで参加者の顔がとても生き生きと輝くひと時です。患者さん各々で楽しみにしている内容は違います。サロン参加後は、声が出て思いを伝えられる、笑顔が増えた、見当識が保たれる、服薬管理に繋がった、身体拘束解除などの変化がありました。感染対策を行いながらコロナ禍でも継続し、震災後も病棟から開催依頼があり継続しています。デイケアでは、普段と違う表情や姿があり、ご家族も大変喜ばれ病棟看護師や管理者と共に看護の楽しさややりがいを感じています。
- また、看護研究活動についても多職種チームで取り組んでいます。昨年のテーマは、排便、拘縮予防等であり、学会発表への支援ができました。身近なリサーチクエスチョンを研ぎ澄まし研究がまとまっていく過程を通し、スタッフ自身が様々な考え方やスキルを高めていく様子から私自身も刺激を受け、新たな知見に触れる面白さを体感する日々です。
- 今後も患者さんがより自分らしくすごせるよう興味・関心を探ること、日々のケアを研究に繋げ患者さんの思いを大切にしたチーム活動を行っていきたいです。
- 田本奈津恵(たもとなつえ)
- 1995年国立病院機構七尾病院入職、2012年老人看護専門看護師の認定を受ける。
-
Vol.23-1急性期病院での認知症ケア ~最善のケアを共同して考える~
- 2020年認定 認知症看護認定看護師
多摩北部医療センター
榊原 良 - 私が、現在勤めている病院は東京都北多摩北部地域の地域医療支援病院として急性期中核病院の役割を担っており、地域の高齢者が多く入院しています。また、急性期脳梗塞などの脳血管障害やパーキンソン病、アルツハイマー病による認知障害を患っている方も多く入院されています。また、ICUから病棟への転入などの環境の変化により、過活動せん妄を起こす患者も多数います。
- 現在、消化器外科・内科の病棟看護師として勤務しながら、月に2回、院内の認知症ケアチームでの院内ラウンドとコンサルテーションを行っています。病棟では、日々のケアの質向上、手術や検査の前後で、せん妄を発症する可能性が高い患者のせん妄予防ケアなどをロールモデルの役割を果たしながら、日々病棟スタッフと実践しています。こうした方がいいと指示的になるのではなく、一緒に最善のケアを考えて提供することが大事だと考えて活動をしています。コンサルテーションの場面では、病棟から危険な行動があるので対応をお願いしますと問い合わせをもらうことがあります。その一方で危険行動がない人は、対応しなくても大丈夫といわれることがあります。これは、認知症の方=危険な行動がある人、手がかかる人というイメージを持たれているのが原因だと考えます。このイメージを変えてもらうために、認知症患者の潜在する不安やそれに対する対応の仕方をカンファレンスを通じて発信しています。
- 今後の展望としては、院内デイケアを定期的に開催することができたらと考えています。治療の時間以外、寝たきりでいる患者の生活リズムを整えること、患者と楽しいひと時を共有することで信頼関係を構築し、よりよいケアにつなげることを目的に準備をしています。
- 榊原 良(さかきばら りょう)
- 老人保健施設の介護士として2年半、社会福祉協議会で社会福祉士として1年間勤務。その後、社会福祉協議会での雇用形態を週1勤務の臨時職員に変更してもらい、府中看護専門学校に入学。2011年看護師免許を取得し、多摩北部医療センターに入職。神経内科、内分泌代謝内科、消化器外科・内科病棟などで勤務。2020年に認知症看護認定看護師の認定を受ける。
-
Vol.23-2介護老人保健施設での取り組み ~看護師と介護職の連携を目指して~
- 2016年認定 老人看護専門看護師
介護老人保健施設 ライフプラザ鶴巻
石川亜衣 - ライフプラザ鶴巻は、「少しでも永く住み慣れた地域で暮らし続けよう」をモットーに、施設・居宅サービスの提供を通して在宅介護の支援を行うことを理念に掲げる介護老人保健施設です。私は入所サービス部門に副主任として所属しており、利用者が生活する療養棟で日常生活援助や健康支援を行っています。
- 私が老人看護専門看護師の認定を受けた当初、施設の誰も専門看護師を知る人はいませんでした。私自身も、施設でどのように役割を発揮していけば良いのか模索するところからの始まりでした。
- その過程で取り組んだことのひとつが、看護職と介護職が連携できる環境づくりです。看護師が医療処置や服薬管理だけを行い、介護職が排泄介助や入浴介助を行うというように、業務で役割を区別し分担すると、利用者へも業務だけが提供され、生活を支えるという視点が見失われやすくなります。看護師は身体的・心理的・社会的健康の側面から、介護職は生活の快適性の側面から、それぞれ観察とアセスメントをして利用者を援助することを目指し、連携の形を探っていきました。職種や役職を越えて職員同士で話し合いを重ね、利用者の普段の状態を把握した上でちょっとした変化に気づくことや、お互いの専門性や役割を理解し合う姿勢をもつことの大切さを共有しました。
- ある時、普段は自ら車いすで移動し食事の席に向かってまっすぐに座る利用者が、その日は席に対して斜めに座っていることに1人の介護職が気づき、看護職に報告がありました。その場ではバイタルサインを始めとした観察で変調は認められませんでしたが、念のため経過に注意していたところ翌朝高熱が出たため、すぐに病院受診となりました。結果としてその方は入院となったのですが、介護職がその方のちょっとした変化に気づき、看護師と共有したことで、早期発見・早期対応に繋がりました。
- 施設で暮らす高齢者が健康にその人らしく過ごすためには、多職種連携は欠かせないと考えます。これからも、多職種が専門性を発揮して高齢者のその人らしい生活を支えていけるよう、活動を続けていきたいと思います。
- 石川 亜衣(いしかわ あい)
- 高齢者の多い病院で急性期から回復期の実践を経て、2011年に三喜会介護老人保健施設ライフプラザ鶴巻に入職。2016年に老人看護専門看護師の認定を受け、高齢者施設における看護実践や高齢者ケアに関わるスタッフの教育の他、高齢者サロンでの講演など地域での活動も行っている。2023年度は聖路加国際大学で認定看護師教育課程(認知症看護コース)の教員も兼任した。
-
Vol.22-1急性期病院における特定行為研修を活用した認知症看護の実践
- 2014年認定 認知症看護認定看護師
国保直営総合病院 君津中央病院
高梨敬子 - 私が勤務する国保直営総合病院 君津中央病院は、地域の基幹病院として、三次救急医療、がんや脳血管疾患などの高度医療、周産期医療、災害時医療等を提供しています。
- 私は 現在、消化器内科病棟に所属しながら主に認知症ケアチームの専任看護師として 組織横断的に活動しています。認知症ケアチームでの支援過程では、向精神薬が適切に使用されていないことや全身状態が不安定になりやすく薬剤の微調整が必要な場面が少なくないこと、薬物治療を行っていても、認知症やせん妄ケアが十分でないため症状緩和につながりにくいという困難点がありました。そこで、対象の身体的特徴を的確にとらえ、病態の変化や薬剤を包括的にアセスメントする力を強化したいと考え、2018年に特定行為研修「栄養及び水分に係る薬剤投与関連」と「精神及び神経症状に係る薬剤投与関連」を受講しました。研修修了後の実践では、臨床推論やフィジカルアセスメントを学んだことが強みになっています。呼吸器系の疾患で入院となった認知症をもつ患者様の不眠時・不穏時指示の薬剤投与について病棟看護師から相談がありました。その患者様は、夜間、中途覚醒した際に、混乱や焦燥から体動が活発になり酸素需要が増すことで息苦しさも増強し、さらに興奮状態になる悪循環から再入眠が困難となり、不穏時指示を2回投与したところ翌日過鎮静となってしまいました。そこで、中途覚醒時の混乱の緩和に向けたケアについて伝えるとともに、精神症状の評価や投与する薬剤の特徴から何を目的にその薬剤を投与するのかなどについて病棟看護師と共有しました。以降、中途覚醒時の混乱は減少し、再入眠できない時は、不眠時指示の薬剤を投与することで、次第に睡眠覚醒リズムが整い追加投与もなくなりました。
- 特定行為研修を活用し、身体疾患の合併による影響のアセスメントや精神症状の評価を合わせて行うことで、自身の思いや苦痛を的確に表現できにくい認知症をもつ患者様の全身管理や症状緩和につなげることができるのではないかと感じています。また、単に薬剤を提案・調整するのではなく、薬剤調整の目的や身体へ与える影響を看護スタッフへ伝えることで、有害事象を防ぐなど、看護の質の向上や安全な医療の提供につなげることができるのではないかと感じています。今後も、認知症をもつ患者様が、安全で安心して治療にのぞめるよう実践していきたいと考えています。
- 高梨 敬子(たかなし けいこ)
- 1996年に君津中央病院に入職し、2014年に認知症看護認定看護師の認定を受ける。2018年 特定行為研修修了(「栄養・水分に係る薬剤投与関連」、「精神及び神経症状に係る薬剤投与関連」)。現在、チーム活動を中心に組織横断的に活動している。
-
Vol.22-2急性期病院で高齢者が安心して治療を受けられるために
~高齢者の意思を尊重したケアを多職種チームで実践する~ - 2019年認定 老人看護専門看護師
神戸市立西神戸医療センター
森本景子 - 私の勤務する神戸市立西神戸医療センターは、「神戸西地域に根づいた安心・安全な医療をめざします」を基本理念に、神戸西地域の中核病院として救急医療、がん診療をはじめとする高度専門医療、結核医療などを提供する病院です。私は現在、入院病棟でスタッフナースとして勤務し、週2日は高齢者・認知症サポートチームの看護師として院内を横断的に活動しています。
- 老人看護専門看護師の認定を受けてから特に力を入れている活動が2つあります。1つ目は、入院病棟における高齢者ケアです。病棟では、高齢者が手術目的で入院をすることが多く、疼痛や急な環境の変化に戸惑い、せん妄を発症することも多くあります。そのため、病棟スタッフとともに高齢者の身体の特徴や認知機能を踏まえたケアを実施し、合併症や二次的合併症を予防して手術を無事に終えて生活の場に戻ることができるように看護実践をしています。また、週1回病棟看護師と協力して感染予防対策を実施しながら院内病棟デイケアを実施しています。デイケアの日は夕方の焦燥感が軽減され、夜間はよく休めるという高齢者にとっての良い効果が出ており、医療者も効果を実感しています。
- 2つ目は高齢者の治療に関する意思決定支援です。医学的には手術が必要な状態でしたが、「痛くないから、手術はあまり。食べることは好き。」と話す認知症がある高齢者と関わりました。高齢者、医療者、施設の職員で何度も検討を重ね、おいしく食べることを支えるために手術することを決定したものの、術後の身体の回復に時間がかかり、本当に手術をしたことが高齢者にとって善かったのだろうかと私自身悩むことがありました。しかし、高齢者の力を信じて医師、リハビリ職員、看護師と高齢者の目標を共有し、協力してケアをした結果、次第に回復し、「おいしいな。」と食事を食べ、元の生活の場所に戻ることができました。この事例を通じて、高齢者の意向を中心に据え、何が最善なのかを話し合い、持っている力を信じ、目標を共有してケアを行う過程が大切であると感じました。
- 今後も高齢者からたくさんのことを学び、悩みゆらぎながらも活動を続けていきたいと思っています。
- 森本 景子(もりもと けいこ)
- 大学卒業後、神戸市立西神戸医療センターに入職する。消化器外科内科病棟、脳神経内科・耳鼻科・皮膚科・乳腺外科の混合病棟で勤務する。ある高齢者のケアがうまくいかなかったことがずっと心残りで高齢者看護に興味を持ち、院内留学制度を利用して大学院に進学し老年看護学を学ぶ。2019年に老人看護専門看護師の認定を受ける。
-
Vol.21-1終の棲家で最期まで「私らしさ」を支えるケアを目指して
- 2016年認定 認知症看護認定看護師
株式会社東急イーライフデザイン グランクレール立川ケアレジデンス
坂牧 恵 - 私が勤める株式会社東急イーライフデザインは「私らしくを、いつまでも。」を支えるため、東京と神奈川にシニア住宅15か所・介護住宅8か所・カルチャースクール等の運営(2023年8月1日現在)を展開しています。
- 私は介護付き有料老人ホームに勤務し、ご入居者の日々の健康管理や経管栄養等の医療行為、日常生活の援助を行っています。また、自部署での認知症ケア研修開催や会社での認知症多職種研修に講師として参加し、知識不足から不適切なケアとしてご入居者へ不利益を与えることのないよう、認知症ケアの質向上を目指して活動しています。
- 老人ホームは終の棲家となるため、入居時から最期を見据えてケアプランをたて、居心地良く第二の我が家のように過ごしていただけるように支援します。日々、介護職員をはじめとした多職種でその方にとっての最善のケアを模索しています。老化や中核症状、表出されている行動の理由をアセスメントできるようにアドバイスをしたり、考えるきっかけを作ることが私の役割であり、やりがいを感じています。
- BPSDのなかにはケアだけではどうにもならないこともあるため、訪問診療医と連携し、薬物療法も実施します。薬物療法を開始した時は漫然と継続しないように、出現する可能性のある副作用を介護職員と共有し、観察・評価をしています。
- 看取りケアも提供しており、認知機能低下などから苦痛症状を適切に訴えることができないご入居者のアセスメントやケアの見直しを多職種で実施しています。日々行っているカンファレンスでは、ご入居者だけでなくご家族へのケアに対しても、固定観念にとらわれない様々なアイデアが介護職員からも出され、勉強になります。
- 認知症看護認定看護師として、時にリーダーシップをとりながら、終の棲家で「私らしくを、いつまでも。」を支え、よりよいケアの提供に貢献できるよう活動を継続していきたいと思います。
- 坂牧 恵(さかまき めぐみ)
- 2016年に認知症看護認定看護師の認定を受ける。社会医療法人大和会武蔵村山病院の認知症疾患医療センターで専従相談員として活動後、2020年より現所属。
-
Vol.21-2「高齢者のこれまでの人生」を多職種チームと共有し最善のケアへつなぐ
- 2010年認定 老人看護専門看護師
江別市立病院
山下 いずみ - 私の勤務する江別市立病院は、昭和26年に開設された、急性期医療を担う地域の中核病院です。当院は、「いたわりの心をもって患者さん本意の医療を提供する」という理念を掲げ、多職種チームで取組んでいます。当院を利用する患者の60%は70歳以上の高齢者であり、そのうち40%が認知機能障害を抱えています。
- 私は、現在、患者支援センター・認知症疾患医療センターに所属し、入退院支援や療養相談、さらに、認知症ケア・精神科リエゾン合同チームの専任看護師として、多職種チームとともに高齢者ケアを実践しています。
- 私が活動の中で大切にしていることは、「高齢者のこれまでの人生」を多職種チームで共有し、高齢者にとって最善のケアへつなげることです。
- 先日、独居の認知症高齢者(70歳代、男性)が大腸がんに罹患し、ストーマ造設術の目的で入院してきました。ストーマ装具交換の手技をなかなか覚えることのできない高齢者に対し、多職種チームの中には、自宅へ戻ることは困難ではないかと考えるスタッフもいました。そこで、これまでの高齢者の人生を多職種チームで共有しました。高齢者は、認知症をもちながらも数年前に自宅で妻を看取った経験があり、現在は、妻との思い出がある自宅に帰るために、ストーマ装具交換の手技獲得を目標とし、入院生活を送っていたのです。高齢者の人生背景を知ったスタッフは、「手技獲得ができない高齢者」から「手技獲得をしようとしている高齢者」へと、見方を変えました。そして、多職種チームの思いがひとつになり、退院支援に取組むことができ、その結果、高齢者は自宅へ戻ることができました。
- 「高齢者のこれまでの人生」を知ることにより、高齢者の希望に共感し、希望を叶えるための支援を多職種チームで建設的に考えることができます。これからも院内外で高齢者に関わる仲間とともに高齢者にとって最善のケアを考え、実践していきたいと思います。
- 山下 いずみ(やました いずみ)
- 1997年3月札幌医療福祉専門学校卒業。同年4月から看護師として江別市立病院に勤務。2008年北海道医療大学大学院看護福祉学研究科修士課程修了(老年看護学専攻)後、2010年12月日本看護協会が認定する老人看護専門看護師の資格取得。 現在は、患者支援センター・認知症疾患医療センターの看護師長として勤務。
-
Vol.20-1認知症看護認定看護師としての視点の重要性について
-小さな気づきが認知症看護を考えるきっかけになる- - 2020年認定 認知症看護認定看護師
国立療養所大島青松園
谷川貴浩 - 私は、香川県高松市の瀬戸内海に浮かぶ小さな島、ハンセン病療養所の国立療養所大島青松園に勤務しています。国の隔離政策により、故郷や家族から引き離され、病気が完治した後も隔離され続けたハンセン病回復者が暮らしています。
- 認知症看護認定看護師としての活動は3年目で、認知症ケアチ-ム会での活動、各部署のラウンド、相談業務(コンサルテ-ション)、研修会の企画・実施、入所者を対象とした認知症予防等の講話を、園外の活動としては、地域の「認知症の人と家族の会」での講話、看護学生への講義などを行っています。このような活動を通して、認知症を持つ人を一人の人として尊重し、その人の視点や立場に立って行う認知症ケアの考え方を伝えたいと考えています。
- 各部署の看護師、介護員・MSWで構成された認知症ケアチ-ム会では、認知機能障害のある入所者のケア方法について事例検討を行っています。ある日の事例検討では、認知症の進行により今まで自分でできていたことが徐々にできにくくなり、日常生活において介入が必要な状況でも、「人の手を借りてまで生活をしたくない」と訴える入所者に対して、今までと同じような生活を送るためにはどのような支援方法が必要か、ICF(国際生活機能分類)の生活機能モデルを使用し検討しました。認知機能の低下により自己服薬が困難になりましたが、「できない」ではなく「できにくくなっている能力」として捉え、ハンセン病後遺症による手の変形はあるもののコップは自分の力で持って飲むことができる能力を「できる能力」として捉えました。支援方法として、内服薬をコップの中にスタッフが介助することで自分のできる能力により、内服薬を自分の力で服用することが可能になりました。
- 認知症になるとできないことが徐々に増え生活の困難さが増えます。しかし何もできなくなると考えるのではなく、私達介助者が小さな気づきを大切にし、残存機能を適切にアセスメントすることで認知症の人のできる力の発見と継続に繋がります。そのことは、認知症の人の自尊心や尊厳を保つために重要なことだと考えます。
- 認知症看護認定看護師に対してスタッフは大きな期待を持つと思いますが、大きなことをすることが認定看護師ではなく、認知症看護認定看護師の小さな気づきが、スタッフの今までにない認知症看護を考えるきっかけになる役割があると考えています。これからも認知症看護認定看護師として、認知症の人の自尊心、尊厳を尊重した質の高い看護実践、相談、指導ができるよう精進していきたいと思います。
- 谷川 貴浩(たにかわ たかひろ)
- 看護師免許所得後、精神科病院を経験、2004年に国立療養所大島青松園に入職。 2023年より副看護師長として勤務している。たとえ認知症を患っても人生の終焉を住み慣れた「大島青松園」で安心して自分らしい暮しを続けることができるような環境の施設を目指したい。
-
Vol.20-2高齢者の意思が尊重された日常生活が送れるように、看護師の困難と向き合う
- 2014年認定 老人看護専門看護師
滝川市立高等看護学院
菅谷清美 - 私は看護専門学校に勤務しており、老人看護専門看護師としての活動は、病棟でのコンサルテ-ション活動が中心となります。外部からのコンサルテ-ションのため、病棟師長と話し合い、自分の活動が病棟目標達成に繋がることを意識しています。
- 相談内容の多くは、認知症ケア、せん妄ケアです。認知症ケアでは、看護師よりケア方法について相談を受けることが多いのですが、コンサルテ-ション後、迷いが解決した看護師は、主体的に、より良いケアを探求するように変化していきます。以前、精神的に落ち着かず口腔ケアが難しい認知症の方のケア方法について看護師より相談がありました。コンサルテ-ション後、看護師が認知症の症状を踏まえ不安が軽減するように関わり苦痛を緩和することで、認知症の方は最期まで穏やかに過ごすことができました。さらに、その看護師は自ら、より良いケアを目指し、経口摂取の可能性についてカンファレンスで検討していきました。認知症の方が亡くなる数日前に笑顔でプリンを摂取していた姿は今も印象に残っています。
- せん妄ケアにおけるコンサルテ-ションでは、発症要因の特定と同時に、高齢者の「苦痛」や「望み」を知ることの大切さを相談者に伝えさせてもらっています。せん妄状態の時は意識レベルの低下により、言葉で思いを伝えるのが難しいことがあります。しかし、活動を行っていくなかで「これ(点滴)はずして」と叫ぶ言葉が「トイレへ行きたい」という希望であったり、「雪が降っている」という幻視が「寒さ」という苦痛の訴えであるという言葉にならない思いが含まれていることを、高齢者をはじめスタッフ等との関わりのなかから学ばせてもらいました。思いを知るためには必ず言葉にヒントがあると考え、高齢者の生活状況や今までの人生を踏まえ、話しを聴く視点をスタッフと共有しています。
- 日々のケアにおいて高齢者が「何に苦しんでいるのか」「何を望んでいるのか」を知り、意思が尊重された生活が送れる事が大切であり、そのことがACP(Advance Care Planning)にも繋がっていくと考えています。そのためには、これからも相談者である看護師達の困難と向き合いながら、活動を継続していきたいと考えています。
- 菅谷 清美(すがや きよみ)
- 1987年に滝川市立病院に入職。内科、泌尿器科病棟で勤務後、1996年滝川市立高等看護学院に異動、現在に至る。2014年に老人看護専門看護師の認定を受ける。
-
Vol.19-1地域中核病院の認知症看護認定看護師として果たす役割を模索して
- 2019年認定 認知症看護認定看護師
医療法人恒心会おぐら病院
松山美鈴 - 私が勤務する社会医療法人恒心会おぐら病院は、鹿児島県大隅半島の中心に位置する鹿屋市にあり、整形外科、消化器外科、脳神経内科の三つの急性期病棟と二つの回復期リハ病棟で216床のベッドを有しています。鹿屋市は、県下第3位の人口10万人を有する市で、高齢化率は30%未満ですが、隣接する自治体は40%を超え、県下でも有数の高齢化率が高い地域となっています。このような状況に応えるように、同法人は介護事業部をもち、老人保健施設や訪問系サービス等を展開しており、地域に開かれた組織を目指しています。
- 私は、認知症看護認定看護師の資格を得て、回復期リハ病棟の管理者をしながら多職種を交えた認知症ケアチームを立ち上げ、組織横断的に活動してきました。しかし、信頼関係の構築や環境調整等では認知症患者への対応は不十分で、不安が強くなる患者や家族、疲弊するスタッフを目の当たりにし、自分の限界や知識不足を感じる日々が続きました。そこで薬剤調整など学びを深めたいと考え、2022年に特定行為研修「栄養・水分に係る薬剤投与関連」と「精神及び神経症状に係る薬剤投与関連」を修了しました。
- その後、新たな取り組みを始めました。入院当日に「せん妄のハイリスクと予測される患者と家族」を対象に、せん妄についての理解を深め、不安を払拭できるようにパンフレットを用いて説明する場、薬剤投与に対して評価する機会を設けました。その中で、てんかん発作や脳転移による認知機能の障害が疑われ、専門医につなげたケースがありました。薬剤は投与される前後の総合的なアセスメントが重要であり、それは多職種と協働しながら成り立つものです。その中で、患者、家族の最も身近な存在である看護師として、安心・安全の視点を忘れず取り組んでいこうと思っています。入院する前から退院するまで関わることで、自分の果たす役割が少し見えかけているところです。
- 今年度は懸案になっている高齢者の大腿骨近位部骨折術後の誤嚥性肺炎予防に関して、脳卒中リハビリテーション看護、摂食・嚥下障害看護、手術看護の各認定看護師をはじめ、病棟スタッフ、セラピストたちを巻き込み、取り組んでいきたいと考えています。
- 松山 美鈴(まつやま みすず)
- 1998年医療法人恒心会おぐら病院に入職。急性期病棟、法人内老人保健施設、回復期リハビリテーション病棟を経験し、2019年認知症看護認定看護師資格取得。現在は患者サポートセンター看護師長として勤務している。
-
Vol.19-2在宅だからできる!インフォーマルを含めた多職種での高齢者ケアをめざす
- 2015年認定 老人看護専門看護師
複合型サービスじゃんけんぽん観音寺
佐藤文美 - 複合型サービスは2015年の制度改正により看護小規模多機能型居宅介護(以下、看多機)へ名称変更されました。現在全国で800か所を越える看多機が運営されており、通い、泊り、訪問を組み合わせた柔軟なサービス利用ができることが強みです。私が所属する複合型サービスじゃんけんぽん観音寺は、2023年5月で開設から10年目になります。お隣は保育園で子供たちの元気な声が聞こえたり、目の前には農園が広がり土に触れる機会が持てたりと刺激の多い事業所です。
- 私は、看多機で「在宅だからできること」を大切にしています。誰でも人は、家での心地よい過ごし方やゆずれない習慣などがあります。しかし、認知症の発症や患っている疾患や障害などにより、在宅生活を断念しなければならない高齢者もいます。断念せざるを得ない要因は何かをアセスメントしできる限りその方らしい暮らしができる方法を考えます。そのためには、アセスメント力やコミュニケーション力が必要で大きな責任も伴います。時には事業所のスタッフのみならず、近所の方やコンビニの店員さんにも在宅生活を見守っていただけるよう協力を求めます。「在宅だからできること」を実現するためには、倫理的な課題に直面することも多くあります。その方の生きてきた物語に思いをめぐらせ、支えているみんなで試行錯誤を繰り返しています。
- その他に、看護学生など実習の受け入れを積極的に行っています。検査機器のほとんどない在宅で、高齢者の身体的な症状や認知症の方の言動をどのようにとらえるかなど、私のアセスメント過程を伝えたり、学生にも一緒に考えてもらったりしています。そして、少しでも在宅領域での看護の魅力や奥深さに触れ、興味を持ってもらえるような指導を心がけています。
- 在宅領域の看護の質向上がますます求められている今、一人ひとりの高齢者と向き合うことと、地域全体を見渡せる多角的な視野とを大切にして、これからも活動していきたいです。
- 佐藤 文美(さとう あやみ)
- 看護師資格取得後、回復期リハビリテーション病棟や脳神経外科などを経験。2014年より認定NPO法人じゃんけんぽんへ入職し、複合型サービス(看護小規模多機能型居宅介護)のケアマネジャー兼訪問看護責任者として活動中。2015年老人看護専門看護師認定、2022年特定行為研修修了(在宅・慢性期領域)。
-
Vol.18-1精神科病院における認知症看護認定看護師としての実践報告
~院内の認知症看護対応力が向上した取り組みを振り返って~ - 2017年認定 認知症看護認定看護師
兵庫県立ひょうごこころの医療センター
杉田顕好 - 私が勤務する兵庫県立ひょうごこころの医療センターは県下精神科病院の中核的役割を果たす基幹病院として、精神科救急病棟、アルコール依存症専門病棟、児童思春期病棟、コロナウイルス感染症病棟、認知症疾患医療センターを有し、時代やニーズに合せた医療やケアを行っています。
- 現在、私は地域医療連携部に所属し地域の医療機関や行政との医療連携や入院調整する役割のほか、認知症疾患医療センターでの認知症ケアに関するコンサルテーション、院内の認知症ケアチーム(以下チーム)での院内ラウンド、認知症看護ワーキング部会、院内・院外・県立病院内の研修講師等、多方面に渡り活動しています。
- ここでは、チームでの活動についてご紹介させて頂きます。当院に入院する認知症を有する患者の特徴として、中核症状や行動・心理症状により、病院や施設、在宅での生活が困難になり入院するのが特徴です。私が5年前に認知症看護認定看護師の資格を取得した際は、病棟看護師が認知症看護に対して困難感を感じる症例が多い状況にありました。そこで、看護部と協働し、認知症看護の基礎教育に注力するとともに、院内ラウンドを開始し横断的な活動を始めました。
- 活動が定着し看護師の認知症患者への対応力が向上しはじめた頃、病棟単位で創意工夫し、必要な環境調整や個別性のある看護を実践していることに驚かされました。それと同時に、それぞれの病棟での取り組みが院内で共有されれば、病院全体の認知症看護対応力が向上するのではないかと考え、認知症看護ワーキング部会を設置しました。事例検討を通じて各病棟の特徴的なケアや対応方法を共有し、事例検討した内容を「対応方法集」として取り纏め、当院オリジナルの対応方法集として、病棟から病院全体へとケアの拡がりを見せたと感じています。
- 最後に、認定看護師としてのこの5年間は、たくさんの人たちと出会い、支えられ、学ばせてもらい、自分では想像しえなかった可能性を拡げることが出来た期間になりました。認定看護師は認知症の人への直接的なケアはもちろんのこと、病院全体での取り組み、地域や関係機関での取り組み等、活動するフィールドは多岐に渡ります。認定看護師として、今の自分に何が出来るのか、自身の知識や経験を活かし最大限どのような支援が出来るのかを模索し、自分を支えてくれる人たちと協働し、認知症の人へのより良い支援が出来るように活動していきたいと思います。
- 杉田 顕好(すぎた あきよし)
- 2010年に兵庫県立ひょうごこころの医療センターに入職し、2017年に認知症看護認定看護師の認定を受ける。
双方向で話し合える関係性をモットーにスタッフと最善のケアを日々模索している。 -
Vol.18-2専門看護師になって10年目~今できることを精一杯に~
- 2013年認定 老人看護専門看護師
順天堂大学医学部附属順天堂東京江東高齢者医療センター 教育課課長
佐藤典子 - 私は、高齢者・認知症看護に関わり、20年以上が経過しました。そして、老人看護専門看護師(以下、GCNS)になって10年目になります。現在の主な活動は、病院の現任教育と地域連携、家族ケアです。
- 高齢者・認知症ケアでは、倫理観の大切さやケア提供者の倫理観がケアに影響することを実感しています。高齢者・認知症の方が、周囲から、またはケア提供者による偏った見方により、適切なケアが受けられていないと感じることもあります。教育課の立場から、全スタッフが倫理について身近に考えられるように、ラダー毎に倫理的問題と思うことや“もやもや”したこと、時にはガイドラインやツールを用いて分析しながら、話し合う機会を研修にしました。スタッフが日常の“もやもや”を認識し、倫理的な課題を感じ、「本当にこれでいいのか」と立ち止まり、高齢者・認知症の方の立場に身を置いて、高齢者・認知症の方の緩和ケアにつながるようにと思っています。
- 地域連携(主に外来)では、高齢者が住みたい場所で生活でき、認知症があっても地域で暮らせるように、外来看護師と共に、受診に来られる高齢者・認知症の方の小さな変化(身なり、行動、“何かいつもと違う”という看護師の直感)に着目し、こちらから声をかけ、支援を開始する体制をつくりました。高齢者の中には、自分の変化や困りごとを自ら相談する方もいますが、中には遠慮してしまう、他人を頼ることはできない等、思いは様々です。地域のケアマネジャーや地域包括支援センターの相談員と協働し、いろいろな人を巻き込みながら、高齢者にとっての当たり前の生活が少しでも守られるように支援しています。また、孤独になりがちな家族のケアにも携わり、家族の居場所づくりを認知症疾患医療センターと共に行い、家族もケアされる人であることを皆さんに知っていただきたいと活動しています。
- GCNSになって10年、立場や役割が変化しても、“今できることを精一杯に”これからも活動をさせていただきたいと思っています。
- 佐藤 典子(さとう のりこ)
- 2002年に順天堂大学医学部附属順天堂東京江東高齢者医療センターに入職。認知症病棟勤務となり、2007年に認知症看護認定看護師、2013年に老人看護専門看護師の認定を受ける。現在は、教育課に所属し、高齢者・ご家族の皆様が少しでも安心して生活できるように、病院と地域の切れ目のないケアを目指して院内・地域の多職種の皆さんと協働し活動しています。
-
Vol.17-1認知症ケアの質向上を目指して-認知症高齢者とのコミュニケーションを大切に-
- 2009年認定 認知症看護認定看護師
愛媛県立新居浜病院
真鍋光子 - 愛媛県新居浜市は高齢化率が32.2%(2020年)と全国平均より高く、当院の入院患者の約70%(小児・産科を除く)は65歳以上の高齢者です。そして、高齢者の入院増加に伴い認知機能障害を認める患者が増加しており、2020年度は高齢者の約13%が認知機能障害を認めていました。そこで、2021年度より認知症高齢者ケアの質向上を目的に、認知症ケアワーキンググループを設置しました。認知症ケアワーキングは看護師長2名、各部署から選出された看護師で構成されています。
- 認知症ケアワーキングで特に力を入れているのは、身体拘束解除への取組みです。現場が身体拘束を必要と判断する視点は「興奮する」等、医療者側の視点が中心となっていました。このため「興奮するのは何故か、何を訴えたいのか」と興奮することが認知症高齢者の訴えであり、コミュニケーションの方法であると捉え、認知症ケアワーキングメンバーや病棟看護師に考えてもらい疼痛や睡眠管理の支援に繋げました。看護師たちは、興奮や大きな声を出すことを”トイレに行きたいから”、”喉が渇いているから”、”疼痛があるかもしれない”等認知症高齢者の視点で原因を考え、ケアを実践しています。
- 2022年度は、新卒看護師と私で認知症高齢者やせん妄発症患者のラウンドをしています。コロナ禍の実習では、患者とのコミュニケーションが十分できなかった現状があります。認知症高齢者とのコミュニケーションを振り返り、自分の考えを述べてもらうようにしています。新卒看護師たちは「緊張する」と話し、会話が途中で途切れてしまう時もあります。しかし、コミュニケーションを振り返り「以前の職業や生活習慣などを知らないとだめだと思った」と反応があります。
- 新卒看護師には、「この人はどんな人だろうか、何を大事にしているのか、何が言いたいのだろう」という意識を持ち関わってほしいと伝えています。そして、新卒看護師にうれしい変化がありました。自分からあまり訴えない患者が、唯一笑顔になるのは家族の話題であることに気づき、意識的に家族の話題を提供、患者は少しずつ自分のことを話すようになり、「家に帰りたい」という意思を表出することができていました。また、ご家族が荷物を持参された時に、患者のご家族に対する感謝の気持ちや、「家に帰りたい」という意思を伝えることもでき、ご家族は「気持ちを知ることができてよかった」と涙を流された、という記録が残っていました。
- 今後も認知症高齢者とのコミュニケーションを大切に、認知症高齢者をとりまく医療スタッフと一緒に考えながら、看護実践を一つ一つ積み重ねて行きたいと思います。
- 真鍋 光子(まなべ みつこ)
- 看護師免許取得後、愛媛県立病院に入職
2009年認知症看護認定看護師の資格取得
2010年愛媛県立新居浜病院に転勤、2018年より地域医療連携室所属 -
Vol.17-2ケアの質と経営に責任をもって
- 2009年認定 老人看護専門看護師
(株)在宅看護センターくるみ 代表取締役
田中和子 - 私は2009年に認定を受け、主に訪問看護ステーションで活動してきました。訪問看護は経営上の厳しさがあり、ケアの質だけを目指していても、組織の理解は得られない現場です。しかし、ケアの質と経営は、本来比例するはずであり、両方に責任をもつ立場でやってみたいと考えました。そして2021年に東京都調布市に株式会社を設立し、深大寺元町訪問看護ステーションを開設しました。
- 事業の将来性と自身の信頼性をアピールして融資を受けることから始まり、場所の選定、スタッフ募集と初めての経験ばかりでした。共に頑張ってくれる仲間に巡り会い、なんとか開設にこぎ着けました。数ある訪問看護ステーションの中から、まだ無名の当事業所にご依頼をいただくことが奇跡のように思え、1件1件、ご縁を感じながら訪問させていただいています。
- また、調布市では9月を認知症サポート月間として様々な催しをしており、今年度初めて調布市訪問看護ステーション協議会も参加団体になりました。私は協議会役員として企画リーダーをつとめ、他の役員と有志のメンバーと共に、市民に訪問看護師の認知症ケアを知ってもらい活用してもらうためのパンフレット「訪問看護の認知症ケア~私たちにできること~」を作成し、配布しました。そこでは、失行などの症状に気づきケアを工夫していることや、言葉にならない苦痛を察知していることや、持てる力に目を向けてケアをしていることなどを事例で説明しています。もう一つの企画として、認知症に関心を持ってもらうために29事業所の看護師たちが、認知症月間のオレンジ色のプレートを自転車、自動車につけ、オレンジ色のマスクをつけて、訪問時に町中を走り回りました。看護師同士が道で出会うと、仲間意識が生まれ、声を掛けあったということや、市民と認知症について話す機会があったという声が聴かれています。
- これからも一歩一歩、歩んでいきます。
- 田中 和子(たなか かずこ)
- 2009年に老人看護専門看護師の認定を受ける。病院と訪問看護ステーションの横断的役割を経た後、訪問看護ステーションで活動。2021年より現職。
-
Vol.16-1身体拘束ゼロを可能にする大誠会スタイル?身体拘束をしない看護ケアから?
- 2017年度認定 認知症看護認定看護師
医療法人大誠会 内田病院
小池京子 - 医療法人大誠会は、認知症疾患医療センターに指定されている内田病院を中心に、さまざまな介護施設を併設し、医療と介護の両面から高齢者の医療・ケアに取り組んでいます。中でも、「大誠会スタイル」の認知症ケアとは、私たちのケアのあり方であり、パーソン・センタード・ケアの考えを基本とした、人として尊重したケアを行い、そのうちのひとつとして、身体拘束をしない看護を実践することを指します。そうすることで病棟での認知症の方の行動・心理症状が改善し、患者さんに最も適した場所への退院を実現しています。
- 「大誠会スタイル」の認知症ケアをグループ全体で、どの職種であっても遂行するには、職員の意識づくりが大切になります。内部研修では、4名の認知症看護認定看護師(以下、DCN)と師長たちが担当する身体拘束体験研修があります。毎年4月には新入職員が身体拘束を体験し “されると嫌なこと”を体験してもらいます。この体験が、人として当たり前の尊厳を守り続けることに繋がります。2014年から認知症サポートチームを設けて、DCNを主に、病棟及び老健にて看護師の巡回やラウンドをおこなっています。その人らしい生活が行えているかなどの状態の評価や、ケアを行う上での職員の困りごとの洗い出しと情報共有、ケアの提案などをおこなっています。DCNの役目は、認知症ケアの教育や研究、データ収集等を担い、現場看護師のレベルアップを図ることがあげられます。例えば、ロールモデルの手法を録画して誰が担当しても同じようにケアができるようにする、など様々な工夫を凝らしています。「大誠会スタイル」の認知症ケアを実践することで、意思疎通が図れ、BPSDが確実に減り、日常生活でもできることが増えます。また、全職員を対象として,法人職員が執筆した書籍をテキストとして勉強してもらい、定期的に確認テストを行なうだけでなく,部署ごとに成績を開示して切磋琢磨しています。こうした「大誠会スタイル」の認知症ケアを見学し、学びたいという外部の方に対しても、身体拘束体験などの研修を行なっています。これまでの外部からの受講生は、認知症の人ご本人や職員の立場で私たちのケアを体験したことで、自院の身体拘束を実際に激減させている病院もありました。
- 認知症ケアが楽しいと思える職員がたくさんいて、笑顔で看護ケアができる法人でありたいと思います。私たち職員は常に太陽のように明るくあたたかい存在でいたい。私は、自分達の行なっているケアを言語化し、「大誠会スタイル」の認知症ケアを伝えていきたいと思います。
- 小池 京子(こいけ きょうこ)
- 1998年に医療法人大誠会内田病院入職。2017年に認知症看護認定看護師の資格取得、認知症サポートチームマネジャーとなりグループ全体の認知症ケアに携わってきた。障害者一般病棟、地域包括ケア病棟フロアマネジャーを経験し、2022年より看護部長となる。
-
Vol.16-2いま・これからの老人看護に携わる看護職の育成・支援に向けて
- 兵庫県立大学看護学部 講師
老人看護専門看護師
中筋美子 - 私は兵庫県立大学に所属し、大学での教育・研究活動を主な役割としています。大学院修了後、医療機関で勤めていた頃と役割は変わりましたが、老年期を生きる高齢者ご本人の視点を大事に活動することは変わらず意識しています。日々これからの看護を担う学生と一緒に、高齢者ご本人がどのような体験をされているのか、どのような看護が求められるのかを考え、学生の老人看護実践への関心が高まるように講義や実習等を通して関わっています。
- また、大学での教育・研究活動とともに、地域の医療機関で実践活動や専門職支援に取り組んでいます。そこでは認知症やせん妄のケア、高齢者の意思決定支援等に関わることが多いのですが、臨床現場で触れた高齢者やスタッフの声から、認知症看護の現任教育や老人看護の技、高齢者の体験世界に関する研究の必要性を感じています。この数年は医療機関の協力を得て、認知症看護実践力の向上をはかる看護師支援プログラムの開発や認知症高齢者の体験世界を明らかにする研究に取り組んでいます。
- これからも老年期を生きるご本人の視点から考えることを常に意識しながら、将来の看護を担う看護職の育成、老人看護の質向上や専門職の支援に寄与できる実践に根差した研究活動に取り組みたいと思っています。
- 中筋 美子(なかすじ よしこ)
- 大学院修了後、一般財団法人住友病院を経て、2014年より現職。2011年老人看護専門看護師の認定を受ける。
-
Vol.15-1認知症の人の思いを代弁し、急性期医療のその先の生活に戻れる継続看護を
目指す - 東京慈恵会医科大学附属柏病院
認知症看護認定看護師
石井晃子 - 東京慈恵会医科大学は1881年に学祖・髙木兼寛が開設した成医会講習所を起源とし「病気を診ずして病人を診よ」という建学の精神のもと、患者の立場に寄り添った全人的医療と質の高い医療を追求している病院です。柏病院は千葉県の東葛地域北部にあり、地域連携しながら多種多様な役割を担っています。私が所属する看護部は、F・ナイチンゲールの考えにもとづき、看護とは「生命力の消耗を最小にするよう生活過程を整えること」と捉え、地域包括ケアシステムにおける急性期医療の役割を発揮するため多職種との協創による患者参画型チーム医療の質向上に取り組んでいます。私は2018年に認知症看護認定看護師を取得後、患者支援センターに所属し活動しています。PFM(Patient Flow Management)の考え方をもとに入院前から認知症患者自身が自らの力を活かした意思決定ができ、治療に続く療養生活の支援をしています。
- 右上顎癌と診断された軽度認知障害(MCI)の患者さんが化学療法と放射線療法を同時に行うことになり、治療選択の場面で悩んでいました。本人は、「先生がやってくれているならどんな治療でも受けます」と医師からの治療提案に前向きな一方で、妻は「治療を受けるのは賛成だけど、私はこれ以上認知症が進んで、私のことまで忘れてほしくない。だから治療を本当にやったらいいのかを考えたい」と思っていました。患者さんは長く新聞社に勤めていた寡黙な人で、受診日や約束を忘れ、新聞の購読や読書が億劫になり、身体的な衰えから長距離の歩行は困難になりつつありました。治療に臨みたい、でも本当にそれでいいのか、副作用に耐えられるのか、治療の後には自宅でまた生活ができるのか、夫婦の思いは揺れていました。短期記憶障害はありますが周囲の人の話を聞いて自ら判断する事はできると捉え、治療を即決せずに可能な限り機会を設けて医師、外来看護師、がん相談看護師、認知症看護認定看護師で患者自身の思いを聞きました。最初は「治療はやるしかないよね」と言っていましたが、普段の生活の様子を聞くと「本を読むことは昔から好きだから図書館に行くよ」「食べる事は得意ですよ。あと、寝る事も得意ね。でも歯が1本ずつ抜けるんだよね。歳かな?」「散歩は時々いくね」と本人が長年大切にしている事や生活のありようが見えてきました。自分の生活も大切にしながら、治療後の生活を一緒に考えると「そんなに大変な治療だったか。じゃあ、少し考えないといけないかな」と、患者さんの思いは変化してきました。私がキャッチした本人と家族の治療への思いや大事にしていることを担当医師、外来看護師と共有しました。後日、再度治療についてお話を伺うと、家族とも話し合った結果「治療をするか迷ったが、治療はいつでも止められるから、やれる事があるなら頑張りたいと思う」と、受診時に意思決定し入院治療を開始することになりました。入院中は定期的に妻に電話連絡を入れること、食後の歯磨きやうがいや入浴など患者さんが行えるように毎日のケア計画をカレンダーに書き込み、認知機能に合わせてアプローチができるよう病棟看護師と情報共有と調整を行いました。また入院前に本人の誕生日を祝った家族写真をテーブルに飾り、訪室時に家族の話題や自宅での生活を話すようにしていきました。最初の1週間は自室が分からなくなることもありましたが、約1月半にわたる治療を無事にのり超えて退院することができました。
- 認知症高齢者の方々の急性期病院での治療は一時的ですが、心身共に大きな負担となります。だからこそ今の揺れる思いを代弁し、家族と一緒に最善を考えていく事が大切だと思います。治療を決定する時から、治療後のその人の生活を見据えた継続看護が私の認定看護師としての役割と考えて今後も取り組んで行きたいと思います。
- 石井晃子(いしい あきこ)
- 東京慈恵医科大学附属柏病院 勤務
1992年 東京慈恵医科大学附属柏病院 入職
2015年 認知症看護認定看護師の認定を受ける -
Vol.15-2住み慣れた地域で在宅生活を続けるための初期支援から年単位のケア
- 2017年度認定 老人看護専門看護師
エム・ケア名東
荒井祐子 - 私が所属するエム・ケア名東は、グループホームと小規模多機能型居宅介護(以下、小規模)を併設する地域密着型サービスを提供する施設であり、現在は小規模の総合ケアマネジャーとして勤務しています。小規模とは「(なじみの関係を作るため)小さい規模で多くの機能を持ち、通い・訪問・宿泊を一つの事業所で行い、24時間の見守り支援を含む」ものです。
- 小規模への相談内容としては、急に認知症が進んだ(何もやらなくなった、食べなくなった、入浴しなくなった)、デイサービスを休みがちになった、徘徊して警察のお世話になっている、退院後の行き先がない・・など様々です。家族が「在宅介護の限界」で相談に来られる方が多く、グループホームは常に満床状態です。
- そこで、小規模を利用しながら在宅生活を続けられるように、利用者と家族の情報収集とアセスメント、そこから生活の再構築を行うことが私の大きな役目です。
- 初期支援では、口腔と全身の清潔に注目しています。口腔の観察を行い、汚れをきれいにします。義歯が合わなくなっている人も多く、嚥下機能と合わせて食事形態や栄養管理を行います。合わせて全身の観察、特に足や足の爪が何年も放置されていることが多いため丁寧にみていきます。その際、利用者自身の抵抗が少なくない為、必要なケアを安全に行えるように看護・介護職員を巻き込んでいきます。教育的立場から、観察ポイントや洗浄・保湿・必要な薬剤塗布の方法を教えていくなど、初めは自ら実践していくことを中心に、その後はスタッフが継続していけるようにリーダーシップを発揮しています。また、利用者の歴史や背景を家族から教えていただくことで、安心できる言葉がけを探っていきます。
- 数か月を目途に利用者の出来ること・出来ないことを多角的にアセスメントし、利用者と家族に対してどのような支援が適切かを判断していきます。家族との関係構築も重要で、介護をねぎらいながら今後(加齢に伴う認知症の進行により)予測される問題の説明と認知症ケアの継続性を保証していきます。初期支援に力を入れることで、その後の年単位のケアが少しでも高齢者・家族・職員にとって安心したものとなるように心がけています。
- 老人看護専門看護師として、高齢者から多くのことを学ばせていただいています。その経験値を言語化・文章化し次につなげていくことが、今の目標です。
- 荒井祐子(あらいゆうこ)
- 看護師免許取得後、京都第一赤十字病院に勤務。大学院(CNSコース)修了後、看護大学助教、急性期病院の勤務の後、現職で2017年に老人看護専門看護師の認定を受ける。
地域に暮らす認知症高齢者の生活において、リスクを予測・対応しながらその人らしい生活が続けられるように日々奮闘している。 -
Vol.14-1困ったときの拠り所となれる認知症看護認定看護師を目指して
- 東芝林間病院
認知症看護認定看護師
宮上 一美 - 当院は「人を大切にする医療を実践して社会に貢献すること」を基本理念とした地域密着型ケア・ミックス病院です。私は地域包括ケア病床に所属し、週2日の活動日を中心に院内で横断的な活動をしています。
- 病院理念のもと病院長はじめ看護部等から、近隣施設や住民の集まりに向けた講師依頼や依頼のあった研修会などには積極的に取り組めるよう勤務等の柔軟な対応があり院外活動も行っています。地域の方が入院した時に、地域の多職種と連携し支援が出来るよう、顔の見える関係作りが必要と考え、多職種が集う研修会等で交流をしています。
- 専門職以外にも認知症の方やご家族とも顔の見える関係が重要と考えています。その一環として、多職種メンバー(地域包括支援センター、薬局、訪問看護ステーションの職員等)と地域の民生委員やボランティアと一緒に『のんびりカフェ』を立ち上げ、認知症になる可能性のある方や認知症の方、介護する家族を支援しています。私は認知症看護認定看護師(DCN)として教育を担当し、のんびりカフェスタッフや地域住民に向けた研修会を企画し、認知症に対するネガティブなイメージを払拭し、認知症だから何かしてあげなければならないと気負わず人として接することが出来るよう支援しています。
- ある日、認知症の義祖母と共に訪れたご家族から「最近ご飯を食べなくなって」との言葉が聞かれました。その場にいたスタッフと共にお話を伺い、「最近家族と同居が始まり、食事は今まで食べていた量で本人の好きな物や食べやすい物を出していました。(水分は)あまり摂ってないです。おしっこが近くなっちゃうのが心配みたいで」等と生活歴や近況について知り得ることができました。高齢者にとって転居は大きなイベントであり、また受け入れる家族にとっても困惑をきたすことでもあります。私たちは、ご本人が馴染みの物を継続して使うことを提案しました。しかし、排便について誰も確認していませんでした。私は、フィジカルアセスメントを行い、腸蠕動音が減弱し濁音があり腸が触れたことから、食欲低下の要因は環境変化だけではなく便秘によるものも要因の一つであると考え、かかりつけの医師に繋ぎました。その後、排便コントロールも良好になり食事摂取量が増え穏やかに生活されている事例を経験しました。些細な言葉から認知症の方やご家族の困り事を把握し解決する糸口を見いだし地域のスタッフと共に支援にも繋げることが出来たと思います。
- 今後もDCNがいることで地域の方が困ったときの拠り所になれるよう、地域の多職種と共に「その人らしさ」を支える認知症看護を提供していきたいと思います。
- 宮上 一美(みやがみ かずみ)
- 2007年東芝林間病院入職し、2017年認知症看護認定看護師の認定を受ける。地域包括ケア病床立ち上げ時から現在まで所属。多職種からなる認知症チームのサブリーダーとして「その人を知ることから始めよう」をスローガンに、組織横断的に活動を行っている。
-
Vol.14-2今までの私、そしてこれからの私
-所属組織の統合再編 老人看護専門看護師としての新たな一歩を踏み出し- - 兵庫県立はりま姫路総合医療センター
老人看護専門看護師
森山 祐美 - 私は、大学院修了後2022年5月1日に閉院した社会医療法人製鉄記念広畑病院に就職し、17年間に渡り老人看護専門看護師として組織横断的に活動を行ってきました。
- 就職当初は、産科や小児科以外の病棟を数か月単位で巡り、ケアを通して高齢者や高齢者を支える人たちの抱える課題を抽出し、ひとつひとつ課題解決を目指していきました。特に、力を入れてきたものに、“せん妄ケアの取り組み”と“摂食嚥下ケアの取り組み”が挙げられます。
- 製鉄記念広畑病院に就職した当初は、「せん妄」という言葉はまだ医療現場において耳慣れた言葉ではなく、治療やケア方法も確立されておらず、過剰な身体拘束が行われるなど高齢者や高齢者に関わる人たちが非常に苦しむ状況にありました。今も目を閉じると、その時の辛そうな高齢者の顔や家族の顔、スタッフたちの顔が浮かんできます。この状況を何とかしなければならないという思いが私を突き動かし、せん妄ケアについて熱く議論でき協働できる医師や薬剤師に声をかけ、2005年9月開始の「せん妄回診」というチーム医療へとつなげていきました。その時々の現場のニーズを捉え、協働できる仲間を増やしながら、「せん妄コアナースの会」「せん妄ケアチーム」「高齢者ケアチーム回診」「高齢者ケアチーム」と活動内容を変化・充実させていきました。
- また、高齢者の口の状態が整っていないことが気になった私は、押しかけるように各病棟で口腔ケアを実施していきました。私の取り組みに賛同してくれた言語聴覚士とリハビリテーション科医師に声をかけ、病棟看護師による摂食機能療法ができるよう調整し、脳外科病棟をモデル病棟として導入することから始め、院内全体へと導入の幅を広げていきました。さらに、管理栄養士とも協働し、院内の嚥下食等食事形態も整え、摂食機能療法に取り込んでいきました。そういった取り組みが功を奏し、院内発症の誤嚥性肺炎は減少していきました。
- 私はこの17年間を通し、高齢者の方々に多くの事を学ばせて頂いたこと、仲間と共に高齢者看護に携わってこられたことのすばらしさを感じています。専門看護師になりたての頃は、気負って反感を買ってしまった事もありました。でも、高齢者や仲間にそれを気づかせてもらい、ここまで歩んでこられたのだと思います。
- 2022年5月1日。勤務していた製鉄記念広畑病院は83年の歴史に幕を閉じ、兵庫県立姫路循環器病センターと統合し、兵庫県立はりま姫路総合医療センターへと生まれ変わりました。病院の規模も倍の736床となり、地域の救急及び高度専門・急性期医療を守っていきます。超高齢社会である現在、老人看護専門看護師である私の使命は何なのか、老人看護専門看護師であり管理職である私の役割は何なのか、常に考え続け、行動に起こし続けていきたいと思います。
- 森山 祐美 (もりやま ゆみ)
- 兵庫県立はりま姫路総合医療センター 勤務
2004年 社会医療法人製鉄記念広畑病院に就職し、組織横断的な活動を開始
2006年 老人看護専門看護師の認定を受ける
2017年 副看護部長を兼務
2022年5月 所属組織の統合再編により、兵庫県立はりま姫路総合医療センターに就職し、看護部次長として勤務 -
Vol.13-1認知症専門病院における認知症看護認定看護師としての活動
- 医療法人社団翠会 和光病院
認知症看護認定看護師
岡田直美 - 和光病院は、埼玉県和光市にある精神科単科の認知症専門病院です。5病棟285床の病床と外来を有し、認知症の診断と治療、認知症の行動・心理症状(以下、BPSD)に対する治療とケア、身体合併症の治療、認知症の終末期ケア、看取りのケアを行っています。開院以来、隔離や身体拘束を行わないという方針のもと、ケアを実践しています。私は、スタッフが認知症の疾患を理解しケアできるように院内研修の講師を担当しています。
- 病棟での私の役割は、ケアの質向上のために、日々スタッフと共に、このケアで良いのかと考え、これで良かったのかと悩み、その時々の最善のケアが実践できるようにサポートすることだと考えています。スタッフには、認知症の中核症状により患者がどのような生活の不自由さを抱えているのかを考えることやBPSDを問題にするのではなく、その要因をアセスメントしケアする重要性を伝え続けています。
- また、認知症の進行にともなって生じる苦痛を緩和し、心地よく穏やかに過ごすことができるように日々の日常生活援助の質を見直し、改善しています。具体的には、美味しく味わうことができる食事援助、リラックスして心地良さを感じられる入浴援助、プライバシーを考慮した排泄援助、髪を整える、ひげを剃る、爪を切る、眼脂を取り除くといった整容など、「日々のケアを丁寧にすることの大切さ」をスタッフと共に日々実践しています。
- 外来では、認知症看護外来を担当し、介護する家族の支援を行っています。家族が抱えている悩みを傾聴し、相談に応じています。介護が切羽詰まった状況で、疲労が強い場合には、サービスの利用や短期的な入院を勧めることもあります。
- 和光病院には、私を含め3名の認知症看護認定看護師がおり、取得を目指す看護師も増えています。今後は、認知症看護認定看護師として、認知症を抱えている方が早期受診できるように支援すること、若年性認知症の患者と家族への支援、認知症の緩和ケアを充実させていきたいと考えています。
- 岡田直美(おかだなおみ)
- 看護師免許取得後、一般病院で呼吸器内科病棟、神経内科病棟などを経験し、2011年和光病院へ就職。
2014年に認知症看護認定看護師の認定を受ける。2017年より病棟師長として勤務している。 - 聖隷三方原病院
老人看護専門看護師
佐藤晶子 - 私が勤務する聖隷三方原病院は、「隣人愛」を基本理念とし「この地域にしっかりと根ざし、住民に信頼される病院づくり」を経営方針とする急性期総合病院です。ドクターヘリを有する三次救急からホスピス、医療型障害児入所施設まで幅広い医療を提供しています。私は専門認定看護室に所属し、認知症・せん妄ケアサポートチーム、倫理委員会等の活動を通じ、急性期病院の高齢者ケアの質の向上に取り組んでいます。その成果のひとつに、身体拘束の最小化の達成があります。運用や記録の整備に加え、看護副部長と専門看護師による(隔)週1回の身体拘束患者ラウンドと病棟スタッフとのカンファレンス、毎月のデータ配信等を継続し、救命救急センター・院内ICU含む病棟(精神科、医療型障害児入所施設除く)において、2020年度以降身体拘束具を使用した身体拘束率は1~3%、10名前後/日で推移しています。カンファレンスでは患者との対話や現在の行動の観察により3要件(切迫性・一時性・非代替性)をアセスメントし、解除に向けた検討を行っています。
- さらに「尊厳を守る」ケアとコミュニケーションの実践を看護部門目標に掲げ、その達成に向け、処置やケア場面での丁寧な説明と同意、羞恥心への配慮など副師長が実践モデルとなり職場内教育を推進するグループ活動を支援し共に取り組んでいます。同時に、専門認定看護師の仲間とともに、排泄、清潔、コミュニケーション、環境の4つの視点から「尊厳あるケア」の行動目標を示し2ヶ月毎にポスターを配布、看護管理者と共に評価とフィードバックを継続し、行動目標の実施率向上がみられました。
- これらの高齢者の人権と尊厳を守る取り組みを基盤に、治療や療養先の選択の意思決定支援の場面では、対話を通しこれまでの生活や価値観にふれ高齢者の思い・希望を聴き取り、探っています。たとえ思いや希望がそのままの形では叶わないとしてもできるだけ近づけ、高齢者の不利益を最小限にするために、多職種と日々カンファレンスや情報共有し、目標を定め具体策を検討し、少しでもよりよい医療・ケアを提供できるよう活動しています。
- 佐藤晶子(さとうまさこ)
- 2000年聖隷三方原病院入職、一般病棟、外来勤務を経て、2015年大学院修了、同年老人看護専門看護師の認定を受ける。認定後病棟管理者を経て、2019年より専門認定看護室に所属し、チーム活動を中心に組織横断的に活動している。











































Vol.13-2
急性期病院に入院した高齢者の人権と尊厳を守る、よりよいチーム医療・ケアの提供をめざして

-
Vol.12-1本人、家族、皆で歩調をあわせて、横並びの関係づくり-地域包括支援センターでの活動報告-
- 認知症看護認定看護師
地域包括支援センターきしろ
村瀬 磨美 - 私の所属する社会福祉法人きしろ事業団は、鎌倉市に軽費老人ホーム、特養2カ所、地域包括支援センター2カ所やデイサービスセンターを持ちます。「ずっとじぶんの道をゆく。」をモットーにご本人の意思を尊重し、その人らしく生きられる場所を作ることを大切にしています。私は地域包括支援センターきしろの保健師として、認知症地域支援推進員かつ認知症初期集中支援チームの担当をしています。
- 当センターが担当する地域全体の高齢化率は35.4%で、中には52%と高い地域もありますが、地域の見守りや助け合いなどのつながりがあります。開業医との連携が進み、医師より直接支援の依頼が入ることも少なくありません。
- 認知症の方が生活する場でおこっている問題は、複雑でどうなっているのかわかりづらいと思うかもしれません。しかし、本人の生活について情報収集を的確に行うことができれば、問題は意外とシンプルだと感じます。何が生活障がいかを確認し、認知機能を補い、BPSDの誘発因子となっている環境を本人、家族、近所の方々、多職種で協力して調整します。
- 家族が同居していない場合は特に、支援者だけで支援体制を組んでしまわぬようにしています。まずは本人の状態を家族に把握してもらい、本人の情報を医療機関、ヘルパーや民生委員、コンビニの店員など生活の様々な場面で関わる方たちと一緒に集めます。その上で、今本人がどのような状態なのか本人と家族に説明します。
- 例えば、指示通りの服薬できていないため、体調が不安定であることが、BPSDの直接要因と判断することがたびたびあります。病院や施設と異なり、在宅の認知症の方が処方された通りに服薬することは工夫が必要です。本人が服薬できていると考えている場合や、服薬していないことに触れられたくない場合もあります。時に、家族や本人に直接薬局へ残薬を持って行ってもらい、状況を薬剤師に知ってもらうことがあります。そして、家族や本人に残薬のことや、そもそも服薬したくないことなどを薬局で相談してよいことを知ってもらいます。本人に許可を頂き、薬剤師に当方からも状況を伝えておいて対応してもらいます。そして服薬できる環境の工夫や具体策を、本人や周りの皆で考えます。
- 様々な意思決定の場面で、本人が説明を受けた体験を忘れたとしても、周りの人が説明し、本人が理解し選択した体験を積み重ねることで、周りと信頼関係を築くことができ、その後のサポートを受け入れる状態になることを体験してきました。本人の状態や、何をサポートすれば生活障がいを補えるのかを伝えることで、本人、家族、支援者、皆が具体策、アイディアを出せるように関わっています。
- 個人への支援に限らず、集団への支援も行っています。家族は、認知症の方へのよい対応を頭で理解できても、今までの関係性から、あるいは家族の孤立によってそれを実践するのが難しくなります。在宅で家族を支えることは本人のBPSD予防に直結します。家族同士をつなぐ一つとして介護者のつどいを年4回開催しています。家族は、家族同士という横のつながりを持つことで支えが強化されます。経験を積んだ家族は語ることで経験を整理し、経験の浅い家族は知識と共感を得られることで、精神的に安定し、その後の支援を受け入れやすくなるなど効果を実感しています。
- 認知症看護認定看護師として、時にリーダーシップをとりながら、本人やその周りの人々と横並びで、共に生活をする者として歩んでいきたいと考えています。
- 村瀬磨美(むらせまみ)
- 小児病棟、精神科訪問看護に勤務後、夫の海外転勤により10数年間の専業主婦を経て、クリニックの訪問看護にて仕事を再開する。2011年より鎌倉市内地域包括支援センターに勤務する。認知機能が低下し、初期対応により、ご本人の療養生活が大きく左右されることを目の当たりにし、専門知識の必要性を強く感じ、2017年に認知症看護認定看護師資格を取得した。2020年度に一年間、退院支援看護師として勤務する。

- 高槻赤十字病院・高槻赤十字訪問看護ステーション
老人看護専門看護師
原田かおる - 当院は大阪の北摂地域に位置する急性期病院です。人道・博愛の赤十字精神を理念に、地域の人々が誇りにする病院となるよう努めています。私は、看護副部長、地域連携部門である患者支援センター副センター長、併設の訪問看護ステーションの管理者として、高齢者ケアの質向上を念頭に活動しています。
- 訪問看護では、高齢者のご自宅までの道のり、家の佇まい、室内の置物など、全てが高齢者・家族のこれまでの人生そのものであると実感します。自身の五感を研ぎ澄まし、感じ取り、その方の価値観、どう暮らしたいかを知り、その暮らしが継続するよう支援させてもらいます。ある高齢者からは「もう、十分生きました、そっとしておいてください」とやんわりと介入を断られたり、「ウジに食べられて死ぬのは嫌なんだ、(支援してもらって)安心だ」など、その人それぞれのお気持ちをお聴きします。その言葉を真摯に受け止め、自身の価値観と照らしつつ、高齢者一人ひとりに学びながら、私たち看護がどう伴走するかを考え支援しています。例えば、介入を断られる場合にはその理由を教えて頂き、その理由が我々の関わり方や配慮で軽減や解消ができるか、などその方の生活、QOLを軸に考え対話をしながらケアを検討します。訪問看護は年単位のお付き合いとなることが多くあります。老いの進行、病気の発症、環境の変化など、高齢者に様々に生じる状況を共に受け止め、共に悩みながら支援する姿勢で、ご本人・ご家族、スタッフ、地域の他職種と語り合い、協働しながら、その方にとっての豊かな暮らしを支えるお手伝いができればと思っています。
- 現在、COVID-19感染拡大が続くなか、地域の高齢者の生活は一変しました。この状況で地域の訪問看護ステーション管理者とさらにつながりあい、助け合いながら、高齢者が豊かに暮らし続けられる地域づくりにも取り組んでいます。
- よりよい高齢者ケアの提供に貢献できるよう、今後も研鑽を続けていきたいと思います。
- 原田 かおる(はらだ かおる)
- 1995年高槻赤十字病院入職。2013年に老人看護専門看護師の認定を受ける。看護部に所属し2017年に患者支援センター副センター長に着任。2019年4月より、兼務にて病院併設の訪問看護ステーションに所属。
Vol.12-2
地域の高齢者・家族が豊かに暮らし続けられるために-高齢者から学び、伴走する-

- 2006年認定 認知症看護認定看護師
日本生命病院
髙原 昭 - 日本生命病院は済世利民を基本理念とする急性期の病院で、大阪府がん診療拠点病院、地域医療支援病院の指定を受けています。訪問看護ステーションを併設しており、地域密着の医療を行っています。
- 私は、認知症看護認定看護師の認定を受け15年目になります。急性期病院と認定看護師教育課程での勤務を経て2年前に現在の病院に就職し、脳神経外科、脳神経内科、皮膚科の病棟に所属しています。急性期病院では、認知症とせん妄のアセスメントは難しく、所属する病棟のスタッフが行うアセスメントやケアについて知りたいと思い、夜勤から日勤に行うウォーキングカンファレンスに毎日参加し、認知症の人の症状やケアについて一緒に考え、転倒転落の可能性がある場合やせん妄、BPSDのある患者さんの対応を話し合っています。
- 病院全体に対しては、多職種からなる認知症ケアチームメンバーと各部署の認知症ケアリンクナースと一緒に帳票類の作成と認知症やせん妄に関する知識の啓発、ケアの方法を話し合い、認知症ケア加算Ⅱから認知症ケア加算Ⅰへの変更に取り組みました。また、せん妄ハイリスク患者ケア加算も取得できるようにしました。
- 認知症ケア加算では、認知症高齢者の日常生活自立度判定で加算の基準を満たした患者さんがリストに上がれば、その患者さんのところにできるだけ早く出向き、認知症のアセスメントを行いスタッフと情報を共有しています。スタッフから「意思疎通ができません」と聞くことがありますが、実際には難聴のため聴こえていない場合があります。患者さんの所にいき、病室での様子を確認し、入眠時には無理に起こさず時間を変えて訪問し、覚醒時に目を合わせて表情の観察をして私をどのように感じているかを確認し、話しかけたり身体に触れたりしてコミュニケーションの方法を考えます。聴力では、どちらの耳が聴こえやすいか確認をし、聴きやすい声の大きさやスピードを評価し、場合によっては補助具を使用して会話を試みます。失語の有無も確認し聴理解の程度を評価しています。これらの評価から患者さんとのコミュニケーションの方法をスタッフに伝えると、「意思疎通できません」と言っていたスタッフも話しかける姿が見られます。また、難聴と思われていた患者さんの中には、耳垢が詰まっていた場合がありました。耳垢をとると「よく聞こえるわ」と聴力が上がることもスタッフと一緒に経験しました。
- また、高齢者の場合は入院時にせん妄を発症することをよく経験します。せん妄があると注意が集中しにくく視線が合わないことがあります。一度に多くの言葉を理解するのが難しくなるため、言葉は短くし、入院している事を伝え、痛みや苦痛の有無を確認し、安心・安楽に療養できるよう対応しています。
- 急性期病院では認知症の人やせん妄の患者さんの生活が見えにくく、本人の言葉を聞かなければ患者さんの“できること”を判断することが難しいです。コミュニケーションができれば、患者さんは何がしたいか、何をしてほしいかをスタッフが理解し、患者さんの“できること”がわかりやすくなります。返事が無いからコミュニケーションができないと考えるのではなく、スタッフに認知症の人やせん妄患者さんと会話を楽しんでもらえるように活動しています。
- 髙原 昭(たかはら あきら)
- 看護師免許取得後、手術室、精神科病院、脳機能研究センター附属病院に勤務し2006年に認知症高齢者看護認定看護師(現:認知症看護認定看護師)の資格を取得する。
資格習得後は急性期病院に勤務し、認定看護師の教育課程での経験をへて、現在は日本生命病院に勤務し急性期病院に入院する認知症者、せん妄の症状がある患者に関わっている。
Vol.11-1
患者さんの“できること”を見極めるために必要なこと-患者さんとのコミュニケーションの推進-

- 老人看護専門看護師
介護老人保健施設エル・クォール平和 看護・介護部看護科長
大久保 抄織 - 私は、在宅支援機能において超強化型に区分される介護老人保健施設エル・クォール平和で看護科長として働いています。当施設の利用目的は急性期治療終了後のリハビリ継続や介護者の負担軽減など様々です。いずれも在宅支援にあたり、高齢者の意思と長い間大切にしてきた価値観や環境、習慣などの過去の生活を尊重することが求められます。そしてこれらを踏まえ、当施設を利用していただく期間の中で、その高齢者の最期を見据えてどこまでの医療を望むのか、どこでどのように過ごしていくことが最善なのかを高齢者や家族も含めた多職種で話し合い共有していくことを意識して活動しています。
- 私は日々のカンファレンスで「本人はどう思っているのだろう?」と多職種に投げかけ、職員と共に確認することを繰り返してきました。例えば高齢者の疲労を考慮し離床の時間を少し遅らせようと提案があったとき、「それでいいのか本人に聞いてみよう」と職員に投げかけ、高齢者の意思を確認する方が先であることを強調しました。すると、「認知症だから答えられないと思い込んでいた」という職員の声が聞かれ、それまで高齢者の意思を確認していなかったことに気づいてもらえました。そして、日常生活の折々で、今日はどの服を着るかなど高齢者の意思を確認し、決めていただく姿が見られるようになりました。
- 高齢者の過去の生活については、委員会活動を通して情報用紙の作成やその活用の定着に向けて試行錯誤を繰り返してきました。過去に目を向けることにより今見ている高齢者がその人の全てではないと理解し、行動の意味や余暇の過ごし方など職員が高齢者との関わり方を考えることにも繋がりました。また、サービス担当者会議を活用し、多職種が集まる場で高齢者の過去の仕事、思い出深いエピソード、家族を看取った経験などを高齢者本人や家族に質問しながら、それらに対する思いも多職種で共有してきました。その上でこの先高齢者がどこでどのように最期までを過ごしたいのかもその場で確認し、高齢者にとっての最善を考える流れを作るよう努めました。委員会を活用し、最期までをどう過ごしたいかについて高齢者へどのように確認していくのか、具体例を挙げて職員に伝えていきました。最近では高齢者と職員とでテレビを見ながら最期までの過ごし方についての希望が話題となることがあり、職員からも高齢者本人の意思を改めて確認し今後について多職種で再共有すべきではないかと問題提起されるなど、施設全体の意識が少しずつ変化していると感じています。
- さらに、当施設が所属する法人内の病院や地域の施設、地域住民に対し研修や認知症カフェ等を通し、高齢者の意思や過去の生活を踏まえた上での最期を見据えた支援の重要性について伝えていくよう努めています。今後も多職種で高齢者にとっての最善を考える機会を増やしながら、施設内外で活動していきたいと思います。
- 大久保 抄織(おおくぼ さおり)
- 看護師免許取得後、脳神経外科や一般外科病棟などを経験し、1997年介護老人保健施設エル・クォール平和開設時より勤務。2014年に大学院を修了し、同年老人看護専門看護師の認定を受ける。現在は看護・介護部看護科長に就き、施設内多職種の教育や施設内外の地域の高齢者の生活の質向上に向けて取り組んでいる。
Vol.11-2
高齢者の意思と過去の生活を踏まえた最期を見据えた支援-高齢者にとっての最善を目指して-

- 地方独立行政法人 長野県立病院機構
長野県立阿南病院認知症看護認定看護師
西森 則子 - 自施設の診療圏は、中山間地域で高齢化率が45.4%と高く、高齢者夫婦や独居高齢者が多い地域です。また、へき地医療拠点病院に指定されていて、医療が行き届かない無医地区へ、巡回診療も行っています。診療圏は不便な地域ですが、その地に暮らす方々は、その不便さを受容したうえで、愛着を持ち生活を継続しています。こうした、自施設を取り巻く状況から、看護部のビジョンを「地域を守り・医療を守り・看護を守る」と掲げています。
- 私は、2014年に認知症看護認定看護師(以下DCN)の資格を取得しました。高齢化の進む地域の要望から、病院の計画に「認知症なんでも相談室」が上げられ、資格取得直後から看護外来として開始しました。認知症の診療体制が無い状態で看護外来を行うには、地域とつながりを作ることが大切だと考えました。そこで、院内の許可を得て地域の保健師会に参加させていただき、認知症ケアに対する研修を行いました。その事をきっかけに、地域ケア会議の出席や認知症に対する出前講座、認知症サポーター養成講座を行い相談しやすい関係性の構築に努めました。地域へ出ることで、当事者や対応に困窮している介護者の方からの相談を受けることが多くなりました。
- アルツハイマー型認知症になった実母の事で、何度も相談に来られた方が「最初は外に出て行ったり、排泄を失敗したり、手を煩わす事が多かった。あの頃は、ずっと続くのではないかと感じていた時に話が出来て楽になった。でも、月日が経ち、じっとしている母を見るとあの頃のほうが良かったと感じる。」と話をしてくれました。相談する方も相談の当事者も、笑顔で過ごせるような関わりが出来るようにしたいと思ったきっかけとなりました。
- 高齢者看護外来は月に1度ですが、当院に通院する患者さんを対象に本人・家族の困り事を把握し、ケアの提案と地域との連携、神経内科の医師と協働し在宅療養を支援しています。
- また、入院中の高齢者や認知機能が低下している方へ、生活の質を維持できるような関わりとして院内デイを計画し、2015年から連日行っています。2016年からは、病院内で「認知症カフェ」を開始しました。DCNとして、認知症カフェを「楽しい場」になるように関わりました。活動には消極的になってくる高齢の方々が、得意な裁縫を教えてくれたり、カラオケで得意気に歌を披露してくれたりしました。季節毎の行事を参加者が中心となって進めたことで、楽しい集いの場となったようです。また、DCNが認知症の話や参加者の様子から家族などへの助言も行いました。相談とは別の立ち位置から地域の方と関わることができました。(昨年4月から、COVID-19の関係で院内開催を休止しています。)
- 地域の方々と関わる活動は私自身の学びになりました。そして、その活動は地域活性化の一助になったのではないかと感じています。現在、COVID-19の関係から地域活動は縮小傾向にあります。今後DCNとして、地域への関わりを検討していきたいと思っています。
- 西森 則子
- 東京都生まれ。
看護師免許取得後、東京大学医学部付属病院勤務。 その後、長野県立阿南病院勤務。
平成26(2014)年 認知症看護認定看護師の資格取得
平成29(2017)年 地域連携室長として入退院調整業務
令和 1(2019)年 病棟看護師長
令和 2(2020)年 副看護部長
*認知症看護認定看護師としての業務を並行して行っている。
Vol.10-1
超高齢化の進む地域での認知症ケア-地域の活性化をめざす取り組み-

- 愛媛大学医学部附属病院
老人看護専門看護師
曽根 司央子 - 私の勤務する愛媛大学医学部附属病院は、松山平野の南東部に位置した自然豊かな環境にあります。愛媛県唯一の特定機能病院であり、「患者から学び、患者に還元する病院」を基本理念に地域に根差した医療を実践しています。
- 私は歯科口腔外科・泌尿器科病棟に所属しています。手術や化学療法など積極的な治療を受ける高齢者が多いのですが、治療に関わる意思決定は家族に委ねられることもあります。特に認知症高齢者のケースでは、治療が進んでいく中で本人の意思が確認できず、スタッフが「本当にこれでよいのか」と悩むことがあります。そのため、認知症高齢者の思いを引き出す関わりについてスタッフと一緒に考えることから始めました。高齢者の意思決定を支援するためのケアについて話し合い、身体状態を良好に保つこと、認知機能や聴覚などの身体的・精神的状態に応じたコミュニケーション方法の工夫の大切さを伝えています。関わり方の工夫によって、認知症高齢者の思いを引き出すことが可能なのだとスタッフが気づくことで、患者さんが大切にしてきた人生についての思いを知ろうとスタッフの意識が変化しています。高齢者の意思決定支援については、まだたくさんの課題があります。まずは、目の前の高齢者を私たちが知ろうとすることが、高齢者にとっての最善を考える第一歩になることを伝えていきたいと思います。
- 急性期病院では治療が優先されますが、治療の後にも高齢者の生活は続いていきます。そのため、疾患や障害とともに生きていく高齢者の生活を整えることも大切となります。食事や排泄といった日常生活を整えること、そして、その人の生活環境や価値観によって形づくられた生活を支えることの大切さについても一つ一つのケースに丁寧に取り組みながら伝えていく必要があると考えています。病棟スタッフの高齢者に対する意識やケアの変化は少しずつです。けれど、小さな変化を積み重ねていくことが今の私にできることだと思います。小さな変化がやがて大きな変化となり、高齢者ケアの質向上に繋がるように病棟での看護実践に取り組んでいます。
- 曽根 司央子
- 2008年に愛媛大学医学部附属病院へ入職。脳神経外科病棟、回復期リハビリ病院勤務を経験。2018年に大学院を修了後、同病院の歯科口腔外科・泌尿器科病棟で勤務。同年老人看護専門看護師の認定を受ける。
Vol.10-2
病棟スタッフによるケアの変化を積み重ねて、高齢者の生活を支える

- 2012年認定
認知症看護認定看護師
須藤照美 - 私が所属する東邦大学医療センター大森病院は東京都区南部医療圏に属し、特定機能病院として高度先進医療を提供しています。三次救急医療機関・地域がん診療連携拠点病院・災害拠点病院などに指定されており、地域の基幹病院としての役割も担い地域医療に貢献しています。認知症看護認定看護師になった当初は、気持ちばかりが焦りプレッシャーに押しつぶされていました。目の前の小さな事を大切にしようと日々、患者さんを丁寧にアセスメントし病棟スタッフと共有していきました。小さな成功体験を積み重ねスタッフと共有する事で認知症看護の醍醐味を実感しました。プレッシャーは役割拡大における気負いだった事に気が付きました。
- 現在は病棟、おたっしゃケアチーム(認知症ケア加算Ⅰのチーム)の専任看護師、高齢者看護外来の3つの役割を担っています。病棟は神経内科・脳外科病棟に所属し直接ケアを行っています。実践とアセスメントを掘り下げる貴重な機会です。病棟での実践がチーム活動に活かせると実感しています。
- おたっしゃケアチーム(認知症ケア加算Ⅰチーム)の活動は週に2回の院内活動で指導・相談を行っています。ネーミングは高齢者を「達者者」と捉えるチームの姿勢を表しています。組織横断的な活動で、部署毎の特徴を捉え病棟スタッフと協働して身体ケアと共に認知機能へのアプローチを行っています。チーム発足当時は安全を重視したケアが行われている事が多かったですが、地道な活動を行う中で認知機能への影響や認知機能の低下を予防する視点に変化してきている事を実感します。
- 高齢者看護外来は月に1度ですが、当院に通院する患者さんを対象に本人・家族の困り事を把握し、ケアの提案と地域との連携、神経内科の医師と協働し在宅療養を支援しています。
- これからも「目の前の認知機能が低下した患者さんへよりよい看護を提供したい。」を忘れずに驕ることなく真摯に向き合っていきます。
- 須藤 照美
- 2004年に看護師免許取得。順天堂大学医学部付属順天堂江東高齢者医療センターに入職。2007年に東邦大学医療センター大森病院に転職し消化器内科病棟に配属。2012年に認知症看護認定看護師の認定を受ける。
Vol.9-1
急性期の認知症看護認定看護師としての活動-取得当初と現在-

- 2018年度認定 老人看護専門看護師
沖縄県立中部病院
東嵩西 寿枝 - 沖縄県立中部病院は中部医療圏に位置し、「すべての県民がいつでも、どこでも、安心して、満足できる医療を提供する」という理念を掲げている急性期病院です。
- 私は入退院支援室に所属し、高齢者の退院支援と認知症ケア・せん妄ケアに力を入れて活動しています。
- 一つ目の退院支援では、入院している高齢者の退院後の生活イメージをもってケアに当たることが必要ですが、入院時の高齢者の状態を『点』で捉えてしまうことが病棟での課題でした。そこで、退院支援カンファレンスでは、入院前の住まい状況やADL、本人の意向等を情報共有し、退院に向けた高齢者の支援目標を看護師間でイメージできるようにしています。このことにより、看護計画は、高齢者の生活史がこれからの入院生活につながる『線』で結ばれます。具体的には、「ひとり暮らしでトイレは自立していたから入院中も促していこう」、「自力で食事をしていたということだから、少しずつ自分で食べられるよう支援しよう」などの目標が設定され、結果として高齢者の持てる力を引き出した退院支援につながっています。
- 二つ目は、「身体拘束を第一選択としない」取り組みを促進するため、認知症ケアコアナース会を立ち上げ、身体拘束を選択した事例について検討を始めています。身体拘束を選択する理由は、“安全に過ごすための協力が得られない”など「看護師が困っていること」が挙げられます。そこで、“なぜ協力が得られないのか、高齢者は何をしたいと考えているのか”を問い、看護師主体の困りごとではなく、高齢者主体の困りごととして捉え直すように討議します。これは病棟看護師が本人の声を丁寧に聴き、観察し、本人の行動の意味を考えることにつながり、看護師が高齢者の困りごとに気づき、身体拘束が解除される成果を上げています。
- これからも病棟看護師との協働を推進し、役割を補完し合いながら高齢者の持てる力を活かす実践に取り組みたいです。
- 東嵩西 寿枝
- 2005年、沖縄県立中部病院に入職。小児科、一般内科、婦人科病棟などで勤務後、2016年より入退院支援室で退院支援看護師として活動。2018年に老人看護専門看護師の認定を受ける。現在は、認知症ケア・せん妄ケアの質向上へ向けた教育的な役割も担っている。
Vol.9-2
高齢者の持てる力を活かす看護師との協働によるケアを目指して

- 2015年認定 認知症看護認定看護師
医療法人徳州会 東京西徳州会病院
瀧島亜希子 - 私の勤務する病院は、「生命を安心して預けられる病院」という理念のもと、地域の急性期医療を担う一般急性期と療養病棟を有する病院です。現在、私は急性期病棟に所属しながら、各病棟のリンクナースと共に、認知症ケアの向上にむけた土台作りを行っています。
- 当院は緊急入院の受け入れも多く、急性疾患を有する認知症の方の入院も少なくありません。私は認定看護師として、業務優先になりがちな臨床の場で、身体抑制を第一選択にしない丁寧なケアの実践を目指しながら日々活動しています。活動の一つとして、認知症ケア委員会を通して、委員会内で自部署のケアの実践を報告し共有しています。共有する際には、看護師側の困り事が実践の焦点にならないように説明し、患者が「困っていること」、「感じていること」を主軸に語れるようにすることを働きかけています。患者の想いを紐解く視点、苦痛や不安がどのように潜在しているのかなど、一つの解決策にこだわらない柔軟な思考ができるように関わり続けています。そして、2年前より、委員会内だけの共有から、看護部全体に範囲を広げ、各部署で取り組んでいる認知症ケアを報告し合い、相互に学び合う機会として事例報告会を開催することにしました。
- 事例報告会は委員会が主催し年に2回行っています。自部署で取り組んだケアから、成果がでたことだけではなく、うまくいかなかった報告も行っています。少しずつですが、業務の枠に縛られない、個別性のあるケアが提供できるようになってきていると感じます。例えば、成功事例では、睡眠障害がある方に、入院前の生活リズムに合わせて、消灯数時間前に入浴ケアを実践した結果、夜間の睡眠が得られるようになったという報告があり、新しいケア方法の一手を共有する機会となりました。一方、うまくいかなかった事例では、入所先を探している患者が、帰宅したいとそわそわしていたからという理由で、一日だけ抑制を行い、精神症状が増悪してしまったという事例でした。抑制を行ったことによる弊害を振り返り、本人の望む自宅への退院は本当に難しいのかという検討までを改めて家族と本人・医師と協議し、最終的に自宅退院をすることができた報告があげられました。これらの報告からも、自分達の行ったケアを振り返り、学びを深め、新たな視点を模索しながら、自分達にできる諦めないケアを追求する姿勢が育まれてきているように感じます。
- 認定看護師としてこのような機会を活かしながら、関わりを積み重ね、当院の認知症ケアに対する意識を少しでも向上できるよう活動を継続していきたいと思います。
- 瀧島亜希子(たきしま あきこ)
- 医療法人徳州会東京西徳州会病院に勤務。2015年に認知症看護認定看護師の認定を受ける。前職場で認知症疾患医療センターでの相談業務や内科病棟の所属長と兼務しながら院内を横断的に活動しケアミックス型病院における認知症ケアの向上に取り組む。2018年から現所属施設にて急性期病棟の所属長を兼務しながら認定活動を行っている。
Vol.8-1
事例報告会を通した認知症ケア向上の取り組み

- 2016年度認定 老人看護専門看護師
島根県立中央病院
立原 怜 - 島根県立中央病院は、出雲市にある「患者と医療者が協働する医療の実践」を理念とする急性期病院であり、国内初の電子カルテを導入した総合病院でもあります。私は入退院支援・地域医療連携センターに所属し、退院調整看護師を中心に、教育や看護研究の支援などの役割を担っています。
- 私が担当している病棟には、整形外科・内分泌代謝科・総合診療科の方が入院され、8割以上が高齢者です。骨折後の回復過程にある方、糖尿病や慢性心不全をもちながら生活を継続していく方、誤嚥性肺炎や認知症・老衰が原因で経口摂取が難しい方など、様々な疾患・病期の高齢者との関わりがあります。
- 緊急入院となった場合、突然日常とはかけ離れた病院での療養が始まります。こうした高齢者に対して、私が一番に取り組まなければならないと考えたことは、せん妄予防および発症時のケアでした。当時は、せん妄という言葉が医療者に知られるようになってきた時期でしたが、個々の経験知による対応が主でした。そのため、看護師へのせん妄のアセスメント・対応に関する研修と併せて、入院前の高齢者・家族に対するせん妄のオリエンテーションを予定入院の方から始めました。せん妄がどのような状態かを説明し、見当識の補完のための時計・カレンダー、感覚器を活かすための眼鏡・補聴器、高齢者の心の支えや会話のきっかけとなる家族写真などの持ち込みをお願いし、高齢者が入院生活に適応することを支えています。今では、看護師から全ての高齢者・家族へオリエンテーションができるようになり、せん妄予防や発症時のケアにも繋がっています。
- また、入院となると普段と違う身体状況・環境により、どうしても高齢者のこれまでの生活(人生史)・発揮されていた力などが見えづらくなってしまいます。そこで、入院時からケアマネジャーや入所施設の担当者からこれらの情報を教えてもらい、カンファレンス等でケアに活用できないか多職種と検討しています。また、退院前・退院後訪問を積極的に活用し自宅での様子を感じてもらうこと、ケアマネジャー・訪問看護師から寄せられた退院後の暮らしぶりをフィードバックすることで、看護師が病院の外へ視点を広げられるようにしています。病院-地域のシームレスな情報共有や医療・ケアへの情報の活用がさらに円滑になるよう、地域関係者とのシステムづくりも進めていきたいと思います。
- 立原 怜(たちはら りょう)
- 島根県立中央病院に入職し救急救命科、腎臓科、泌尿器科、神経内科などで勤務後、2016年に老人看護専門看護師の認定を受ける。せん妄・認知症・倫理などの教育的な役割を担いながら、退院調整看護師として担当病棟での退院支援・退院調整や地域連携に注力している。
Vol.8-2
急性期病院に入院する高齢者を支えるせん妄対策・地域連携

- 2007年認定 認知症看護認定看護師
国立大学法人 長崎大学病院
小渕美樹子 - 長崎大学病院は、県内唯一の大学病院であり、急性期治療や高度先進医療を担う特定機能病院でもあります。年々高齢化は進み、認知症を有する患者も増えてきています。認知症を有する患者が、どこに住んでいても適切な医療を安心して受けられるために急性期病院の看護師は医療と生活の両方の視点をもつことが求められています。
- 認知症看護認定看護師の資格を取得したばかりのころは、急性期病院では在院日数が短いためか、看護師は認知症を有する患者の看護にあまり困っていないような印象でした。看護師長の立場で、自分に何ができるのかと病院内での活動に悩んでいる時期に、家族の会の方から、「病院の看護師さんが認知症のことを知らない。認知症の患者さんや家族のことをわかってほしい。」と言われたことがありました。その時から、私は管理者として、病院の看護師に認知症看護を広め、質的向上を図るのが役割であると決意しました。それからは、認知症看護の質向上に向けた体制整備を行ってきました。
- まずは、専門的な知識を持ち、現場で実践できる看護師を育成するために、認知症看護の専門コースや、認知症看護の院内認定看護師コースを立ち上げました。専門コースは、年に5回のシリーズ研修とし、認知症看護の基礎的知識から学べ、最終的には受講生が経験した困難事例の解決策を見出し今後に生かせることを目的としたものです。この専門コースの受講は、院内認定看護師の資格取得の要件にもしています。また、認知症ケア加算の新設をきっかけに、2017年には認知症ケアチームを発足、各部署にリンクナースの配置を行い、患者の入院に伴う環境変化への適応を支援する体制が整いました。少しずつではありますが、認知症を有する患者への個別性のある看護計画が増えてきています。身体拘束削減についても看護部全体の目標として掲げ、実践のリーダーである副看護師長で取り組む課題としたことで、身体拘束率の減少につながりました。2020年度からはせん妄ハイリスク患者ケア加算の算定を開始し、今後はせん妄対策をより強化していきたいと考えています。
- 認知症であってもなくても、患者の意思が尊重され、できる限り住み慣れた地域のよい環境で自分らしく暮らし続けることができることが願いです。日常の暮らしから離れ、非日常となる急性期病院における入院生活は安心・安全に治療ができる場とし、次の療養の場、生活の場に早期につなぐことが役割だと考えます。そのためには、部署の管理者である看護師長の考えが大きく影響してきますし、他職種との協働も重要です。今後は、管理者育成、チーム活動を強化するための体制整備を推進していきたいと思います。
- 小渕美樹子(こぶち みきこ)
- 看護師免許取得後、国立大学法人 長崎大学病院に勤務。2007年 認知症看護認定看護師の認定を受ける。2020年4月より同院看護部長に就任。病院における認知症看護の質向上に向けての体制整備を推進している。
Vol.7-1
大学病院における認知症看護の質向上に向けた体制整備の取り組み

- 2012年認定 老人看護専門看護師
社会福祉法人 聖隷福祉事業団 聖隷浜松病院
宗像倫子 - 私の勤務する聖隷浜松病院は、3次救急を担う地域の中核病院です。「地域連携」を使命とし、退院支援システムを構築し病棟が中心となり多職種と連携した退院支援に取り組んでいます。私は大学院修了後、在宅・看護支援課で、退院支援看護師として担当病棟の退院・療養支援を通し、高齢者とその家族のニーズを捉えどのように病棟と協働しサポートしていくのか迷いながら活動してきました。
- 見えてきた課題の1つは、看護師が様々な疾患を抱える高齢者の生活を捉える視点に不足があり、医療者側の視点からケアする方向にあることでした。これは、意思決定支援の介入事例の中でも「高齢者・家族と医療者の意向のズレ」として、支援困難となる要因の1つでもありました。そこで、まずは「高齢者を知る」ことを重視し、「入院する前の生活は?」「本人の捉え方は?考えは?望みは?」を看護師に問いかけています。特に自ら意向の表明が難しい高齢者は、院内・外の多職種と連携し、情報収集からケアへ反映できるよう看護師と事例相談、検討を重ねていきました。自宅療養の意向を確認しているものの、病気や治療への理解が十分でないことや、セルフケアの能力の低下、マンパワーの不足から「独居は無理」「介助量が多く在宅生活の継続は無理」など、支援の困り事の主語は看護師になりがちです。看護師の考えの根拠を把握した上で困り事の主語を高齢者として医療、介護上の課題を整理し、ケアの目標・内容を考えていくことを丁寧におこなっています。また、他領域の専門看護師、認定看護師と協働し、退院支援の教育過程の見直し、患者の価値・意向を大切にした意思決定支援について教育に取り組みました。その成果として、入院早期より患者の生活状況の情報を得てケアに反映させ、患者の生活を語るスタッフの姿をよく見るようになりました。
- 現在は、様々な背景を持つ高齢者の退院支援、認知症ケア、せん妄ケアのチーム活動、意思決定支援を地域と繋ぐ地域連携ネットワーク作りに力をいれています。「高齢者を知る」ことを通し、支援の仕組みやケア方法を考え、「高齢者の意向の尊重」を大切にしていくことを伝え続けていきたいです。
- 宗像倫子(むなかた みちこ)
- 1998年聖隷浜松病院に入職。神経内科、総合診療内科などの病棟勤務を経験。2011年大学院修了後、同施設の在宅・看護支援課(現:患者支援センター入退院支援室)で退院支援看護師として活動、入退院支援室の立ち上げに携わる。2012年老人看護専門看護師の認定を受け、2020年より看護部管理室に所属し組織横断的に活動している。
Vol.7-2
高齢者の生活の場と病院をつなぐ、継続したケアを目指して

- 2018年度認定 認知症看護認定看護師
東海大学医学部付属八王子病院
小川和之 - 私は地域医療を基盤とする大学病院に勤務しています。当院では「認知症ケア加算3」「せん妄ハイリスク患者ケア加算」を取得しており、私は病棟業務を中心に院内のコンサルテーションを担っています。活動する中で、日々課題が山積していることを実感しています。臨床現場にいるスタッフは、認知症に対する理解不足や苦手意識があり、対応の難しさに疲弊し、またジレンマを抱いています。その結果、身体拘束や鎮静薬使用に至るという状況があります。
- その状況を改善するため「認知症高齢者の理解」を目標に、スタッフへの認知症ケアに関する教育を行っています。教育内容は、現場で対応に苦慮した事例を各部署から事前に提出してもらい、ディスカッション形式で行う検討会を行っています。 この院内での全体研修を年に4回行うほか、新人を対象とした「認知症の基礎知識・対応方法」の研修や「その人らしさを考える」をテーマとしたラダー別の研修を開催しています。
- 実践を通したスタッフ教育としては、不安から興奮状態になる患者さんに対して、ご本人の生活背景・趣味・嗜好・入院前の生活習慣を家族から聴取し、日中に趣味である英会話の勉強や本を読むなどを取り入れたことで、活動性の向上、睡眠の援助へも繋がり、生活リズムの調整ができ、笑顔で穏やかに過ごせる時間が増えた事例などの実際を紹介しました。その結果、なにもできないと感じていたスタッフから「私たちも実践してみます」とケアへの意欲が変化していきました。
- その他、外来において自宅での介護に疲弊する家族の相談に応じています。病棟では職員を対象に高次脳機能障害や老年期の特徴を交えた認知症看護の研修を行いました。また、「認知症看護の質」というテーマでのオープンセミナーでは院外からも参加者を募っています。
- 現在、新型コロナウイルス感染症によりスタッフ教育にも制限がかかっています。先が見えない現状ですが、病院という特殊な環境の中でも認知症高齢者が自分らしくいられるよう、今後さらに認知症ケアを追求していきたいと思います。
- 小川和之(おがわ かずゆき)
- 前勤務は精神科病院(急性期閉鎖病棟、アルコール専門病棟、痴呆<当時>病棟)。現在は、脳神経内科・外科病棟を経て、整形外科、呼吸器外科病棟に所属しスタッフナースとして従事。認定看護師専用PHSを持ち院内の相談に組織横断的に活動している。
Vol.6-1
スタッフへの認知症教育
―認知症高齢者の理解の促進に向けて―
―認知症高齢者の理解の促進に向けて―

- 2005年度認定老人看護専門看護師
有馬温泉病院
西山みどり - 有馬温泉病院は、昭和47年に創立された医療療養型を中心としたケアミックスの病院です。瀬戸内海国立公園内にあり、みどり豊かな環境と源泉かけ流しの温泉を有しています。
- 私は昨年の4月、看護部長に就任しました。元々、2020年度は電子カルテの導入と、インドネシアからの技能実習生の受け入れが予定されていました。そのため昨年の今頃は、その準備に追われる毎日でした。しかし新型コロナウイルス感染症の流行により世の中は一転し、当院においても感染対策の強化が喫緊の課題となりました。
- 例外にもれず当院も、状態の悪い方を除き完全に家族面会を中止し、玄関先での手指消毒や検温等の策を講じました。加えて職員には、高齢者が多く入院する病院に勤める者としての自覚を持ち、不要不急の外出を控え、徹底的に個人衛生に努めるよう、執拗に言い続けました。これにより、幸いこれまで感染症は予防できましたが、職員の不安と緊張感が増し、高齢者の表情が冴えない日々が続くという事態を招きました。そして初めて、感染症を正しく怖がること、職員のメンタルヘルスを守ること、それが高齢者の生活の質を維持することにつながると気付きました。
- 現在、家族面会に関しては電子媒体もしくは窓越しで顔を見て会っていただくという形をとっています。そして職員に対する私の関りとしては、できる限り足を止め傾聴し、我慢し通しの生活を労うとともに、体調不良時には気兼ねなく休める体制作りに努めています。
- 老人看護専門看護師になって15年、一人の人格を持った人として高齢者と関わること、心地よい日常生活援助を提供することを大切に、『高齢者ケアの質をあげる』の具現化に努めてきました。そしてその達成には、多くの職員の力が必要であると実感してきました。職員一人一人が心身ともに元気で居なければ、高齢者を元気にすることはできません。日常が再び訪れることを願って、今しばらくは高齢者、職員の生活を守りながら感染予防に努めたいと思います。
- 西山みどり(にしやま みどり)
- 2005年老人看護専門看護師の認定を受ける。神戸海星病院勤務を経て、2012年1月より有馬温泉病院に勤務。2020年4月より看護部長として、高齢者が今日を穏やかに、明日を楽しみに生活することができるようスタッフとともに努めている。
Vol.6-2
高齢者、職員の生活を守りながら感染予防に努める

- 2012年度認定
認知症看護認定看護師 小川赤十字病院
大石 留美子 - 私が勤務する病院は、「人口高齢化に対応するために、老年期疾患に対して総合的に取り組みます」を基本方針の一つに掲げチーム医療を実践し、「人を大切にする看護を実践いたします」の看護理念のもと、一人一人の看護師が日々の看護に取り組んでいます。
- 私は看護部に所属し、もの忘れ外来や認知症カフェの運営、認知症ケアチーム・認知症初期集中支援チームの一員として院内外問わず、組織横断的に認知症ケア活動を実践しています。主な活動は、認知症ケアチームの活動になります。週 1回、多職種チームで病棟ラウンドとカンファレンスを行い、認知症または認知機能低下のある方が入院しても穏やかに過ごせるよう、入院早期からサポートをしています。
- 当院は、入院される6割が70歳以上となっており、身体疾患による苦痛や環境の変化などでせん妄や行動心理症状を発症する方は少なくありません。認知症ケアチームラウンドの際、慣れない環境の中で不安を感じ、なじみの環境を求めて「ここはどこですか?」「家に帰ります」などを繰り返し訴える患者さんがいらっしゃいます。それに対し臨床現場では「ここは病院ですよ、さっきも言いましたよね」「入院しているのだから帰れません」など、医療者の当たり前を押し付け、患者さんが混乱し興奮状態となるケースが多くみられます。その際、なぜ患者さんは繰り返し今いる場所を確認し、家に帰りたいと訴えているのかを病棟スタッフとベッドサイドへ足を運び、ともに考えるようにしています。そうすることで、患者さんの言葉の裏にある真の思いを見出すことができ、最善のケアを提供することができるのだと思います。認知症ケアは、私一人の力ではなし得ることはできません。認知症看護認定看護師として、認知症ケアチームメンバーや病棟スタッフ、患者さんを取り巻くすべての医療従事者と協働して認知症ある方の思いを大切にする看護を実践し、入院しても穏やかに生活できるようにサポートをしていきたいと思います。
- 大石 留美子(おおいし るみこ)
- 看護師免許取得後、小川赤十字病院に勤務。2012年認知症看護認定看護師の資格取得。外科・整形外科・内科・精神科病棟で勤務後、現在は看護部に所属して組織横断的に認知症ケア活動をしている。
Vol.5-1
認知症のある方の思いを大切にする看護の実践を目指して

- 2011年度認定老人看護専門看護師
社会医療法人畿内会 岡波総合病院
市川 智子 - 当法人は介護老人保健施設、居宅介護支援事業所、訪問看護ステーションを併設しており、住民が住み慣れた地域で安心して暮らせることを目指し医療や福祉を提供しています。私は、一般病棟、回復期リハビリテーション病棟、障害者等病棟などケアミックスの医療機関に従事しています。
- GCNSとして認定を受けた当初、自分に何が求められているのかわからず手探り状態でした。そのため、積極的に法人内をラウンドし、スタッフや管理者と困り事を共有するよう努めました。その結果、次第に認知症ケア、せん妄ケア、人工栄養法導入の意思決定支援など取り組むべき課題が明確となりました。認知症の知識不足からスタッフが苦手意識を抱いていたため、勉強会で知識を補いながら、スタッフとともにケアの振り返りを行うことで、知識と現象を結び付けられるよう働きかけました。また疼痛や身体拘束、薬剤を要因としたせん妄が引き起こされていたため、せん妄要因や言語的表現が難しい高齢者に対する疼痛の評価方法の周知、せん妄予防・発症時の薬剤一覧表の作成と同時に、医師・薬剤師と連携し電子カルテ上の不眠・不穏時の薬剤を修正しました。ラウンド開始当初、経口摂取が困難な高齢者に対し経管栄養法が導入されることが多かったため、2012年に日本老年医学会が公表した「高齢者ケアの意思決定プロセスに関するガイドライン」を院内に紹介し、人工栄養法の意思決定の際、ガイドラインに沿い支援していきました。この後、スタッフが本人に意向を確認し、多職種間で本人にとっての最善の検討を行う姿をよく目にするようになりました。
- 当初把握した課題については、法人全職種に働きかけられるよう看護職や介護職のラダー教育、事務員研修などに高齢者ケア、認知症ケア、意思決定支援の内容を組み込んでいきました。活動する中で、高齢者に最善の医療やケアを提供するためには、地域住民を巻き込む必要性を痛感するようになりました。地域住民や介護施設職員を対象とした出前講座の開始に合わせ、老化や認知症、終活についての講座を担当し、老いや認知症を自分のこととして捉え、最期の時に向け考えてもらえるような時間を提供しています。
- GCNSの認定を取得し10年が経とうとしています。今後も高齢者へ最善の医療とケアを提供するために、自分に何が出来るのか考え続けていきたいと思います。
- 市川 智子(いちかわ ともこ)
- 2010年大学院を修了し、社会医療法人畿内会 岡波総合病院へ入職。2011年老人看護専門看護師の認定を受ける。
Vol.5-2
高齢者へ最善の医療とケアの提供にむけて

- 2011年度認定
認知症看護認定看護師 姫路聖マリア病院
伊藤大輔 - 私が勤務する姫路聖マリア病院は、兵庫県姫路市の中でも高齢化がすすむ地域にある急性期病院です。地域医療支援病院として地域に貢献することも当院の役割の一つになっています。私は地域連携室に所属し、認知症ケアチーム、認知症看護相談、アウトリーチ活動などで活動しています。認知症ケアチームでは、外来の受診状況や地域の施設の情報が得られやすい地域連携室の強みを生かして活動しています。例えば、認知症の人が入院した当初から、家族歴、支援者の有無、ADLなどの入院前の生活の様子から患者の問題点を早期に整理し、適切に治療や看護が受けられ、退院支援が患者の意に沿うように情報を病棟スタッフや認知症ケアチームメンバーに発信しています。
- 認知症看護相談外来は、利用者が気軽に相談できる場の雰囲気を大事にしています。相談の中には「以前よりもの忘れが多くなった気がする」「会話がこれまでよりも何だかぎこちない」等、相談者本人もしくは家族、主治医が感じる、これまでと何かが違うというちょっとした違和感から相談になることがあります。認知症と思われる症状への気づきと生活への影響を本人や家族、医師と確認し、認知症の原因疾患を診断するかどうかを一緒に考えています。適切な診断と定期的なフォローができるように意識して取り組んでいます。
- 2014年から退院後のケアの継続を目的に、退院時や退院後に居宅や施設を訪問するアウトリーチ活動に取り組んでいます。アウトリーチ活動では、入院中から家の部屋はどのくらいの大きさで、部屋のどこにベッドがあり出入口はどこにあるのか、退院を見据えてその位置で良いのか。一日をどこで何をして過ごしており、その生活が続けられるのか。といった現状を確認し、生活しやすい方法はないかを考えるようにしています。しかし、実際に退院後訪問してみると、想像していたようには生活されていないこともあります。家に帰るとこれまでの風景があるが故に、生活を変えることが難しいことを痛感しました。入院中に病棟で関わっている人、退院後に関わる人と一緒に方法を考えたのですが、そこには限界があることを経験しました。もしかすると急ぎ過ぎたのではないか、無理があったのではないかと考えました。訪問してみなければわからない経験を病棟の看護師とも共有しようと、退院後訪問には病棟の担当看護師を帯同しています。
- 急性期病院に勤務する認知症看護認定看護師として、認知症に関する相談がいつでも誰でも気軽にできることを目指しています。また、入院中、治療優先の環境で自分の力を充分に発揮できない認知症の人の力を引き出すケアを行い、安心して治療を受けることができるようにし、退院後は、その人にあった生活しやすい環境を作るように活動していきたいと考えています。その活動は一人でできるものではなく、家族、病院スタッフ、地域の人等、認知症の人に関わる人みんなで一緒に考えていく必要があると思っています。
- 伊藤 大輔(いとう だいすけ)
- 2007年より姫路聖マリア病院に勤務。2011年に認知症看護認定看護師の資格を取得。内科、整形外科、緩和ケア内科病棟で勤務後、現在は地域連携室に所属し、組織横断的に活動している。
Vol.4-1
認知症の人の生活を関わる人と一緒に考え続ける

- 2008年度認定 老人看護専門看護師
社会福祉法人聖隷福祉事業団 藤沢エデンの園一番館 松本佐知子 - エデンの園は、措置制度のもとで高齢者福祉が提供されていた約50年前に、高齢者のQOLの向上を目指して設立された、本邦初の有料老人ホームです。 高齢者が自立時に入居し(注1)、10年以上暮らした後に逝去する終のすみかのため、入居者とは年単位のお付き合いとなります。健康管理に加えて買物等の生活支援やレクリエーションなどにも関わるため、個々の入居者の健康状態だけでなく、好みや価値観、生活状況と、それらの経時変化も知ることができます。
- このようなケア提供上の利点を生かし、入居者がその時々の状況にあった医療を受けたり、その人らしい生活が続けていけるよう、サポートしています。
- 法人内の転勤を経て、現在は神奈川県藤沢市内の施設で、副園長かつ唯一の看護職員として勤務しています。3年前の着任時より、限られたマンパワーを最大限活用するために、事務系職員を含む多職種が、入居者の変化をいち早く察知したり、適切な対応ができるよう、過去に経験した事例とひもづけたOJTを行ってきました。例えば心不全の事例では、過去の類似事例の症状(例;下肢浮腫、息切れが生じた場面)や転帰(例;入院した)を例示し、目の前の事例も同様の経過をたどるリスクがあることを理解してもらいます。次いで、心不全が悪化しやすい状況(例;疲労、体調不良)と、日頃の生活の様子や訴えを丁寧に観察することが、早期発見と適切な対応のためには重要であることも説明します。さらに、その事例の生活行動で症状が出現すると想定される場面(例;行きつけのスーパーで買物して帰園した時や、園内のフレイル予防の体操教室に参加した後の息切れ)と、対応(例;SpO2測定、かかりつけ医に相談)を伝えます。なお、経験を重ねた人には、観察ポイントと対応は自分で考えてもらうようにします。
- また、認知機能が低下してきた入居者が自律・自立した生活を維持できるよう、介護・医療サービス以外も含めた地域の事業者との連携強化も図ってきました。例えば、金銭管理が難しくなった人に対しては、家族に加えて近隣のドラッグストア等の小売店とも情報共有しながら、対応方法を一緒に考えていくようにしています。
- これらの活動の結果、職員の臨床判断と対応能力および自信が向上するとともに、地域からも「ああ、エデンさんね」と当施設および入居者への理解が深まり、連携がスムーズになっているように思います。
- また最近では、新たなケア方法の導入や従来のケアを改善する際に、Quality Improvementの手法を試みています。一例として、要介護状態の入居者のAdvance Care Planningをより早期から適切に行い、最期の時まで質の高いケアが提供できるよう、同じ市内にある慶應義塾大学と当事業団で共同研究の契約を締結し、研究者と協働して取り組んでいます。
- (注1)要支援または要介護の認定を受けていることが、入居時の要件となっている施設も一部あります。
- 松本 佐知子(まつもと さちこ)
- 2006年に大学院修士課程を修了し、公益財団法人湯浅報恩会寿泉堂綜合病院を経て、2012年より有料老人ホーム「エデンの園」で勤務している。大学と連携して、エビデンスにもとづくケア開発や、施設ケアへの学生の関心が高まるような取り組みに注力している。
Vol.4-2
「終のすみか」の暮らしを支える高度実践看護

- 2015年認定
長浜市立湖北病院
馬場直哉 - 私が勤務する病院は滋賀県の北部にあり、山間部への出張診療を担う“へき地中核病院”です。一般急性期病棟、地域包括ケア病棟、療養病棟があるケアミックス型の病院です。また、介護老人保健施設や介護老人福祉施設を併設しており、地域包括支援センターも院内に開設しています。
- 病院では外来に所属し、認知症サポートチームや院内デイケアで活動しています。認知症サポートチームでは、認知症の人が入院した場合に、所属の強みを生かし、外来受診時の様子や生活歴などの情報を多職種カンファレンスの場で提供し、入院中も在宅での生活とできるだけ差がないように普段の暮らしから想像し、本人に確認しながら環境を整える工夫をしています。
- 院内デイケア開催時は進行役を務め、認知症の人が入院生活で薄れていく季節感を取り戻してもらえるように、季節ごとの懐かしい歌を選んで一緒に歌っています。レクリエーションには体操などを取り入れ、多職種もかかわり、一緒に楽しむことができるようにしています。院内デイケアに参加される方が互いに声をかけ合い、人と人との交流が自然と生まれるような雰囲気づくりを大切にしています。
- 認知症ケア専門講座として院内職員向けの研修を開講していましたが、認知症の人が地域で暮らしていくには、地域の福祉・介護に携わる方々とも繋がり一緒に考えることが必要と思い、現在は院内外から職種を問わず受講していただくようにしています。
- 独居の高齢者や高齢者夫婦で、受診日に来院されないことや、処方された薬を失くして来院されるときなどは、院内にある地域包括支援センターの職員と連携して、今の暮らしを継続できるように対応しています。ただ、どこまで今の暮らしが続けられるか悩ましいケースも多くあります。
- これからも認知症の人が入院した場合、入院生活や地域での生活が「その人らしく」ありうるかという事を、関わる全ての人が考えたいと思えるように取り組んでいきたいと思います。
- 馬場 直哉(ばば なおや)
- 1992年に近江八幡市民病院に入職し、1995年より長浜市立湖北病院に勤務する。2015年に認知症看護認定看護師の資格を取得後、急性期病棟・地域包括ケア病棟を経て、現在は外来に所属し、認知症の人のケアに携わっている。
Vol.3-1
認知症の人の「その人らしさ」が発揮できる生活を目指して

- 2010年認定
国家公務員共済組合連合会 虎の門病院
山元智穂 - 私の勤務する虎の門病院は、「その時代になしうる最良の医療を提供する」という理念を持つ急性期病院です。現在は高齢者総合診療部という多職種チームに所属し、CNS個人、チームとして、主に病棟でのコンサルテーション活動を行っています。
- コンサルテーションの内容で最も多いのは“せん妄への対応”です。当院では緩和ケアチーム、リエゾンチーム、高齢者総合診療部という横断的活動を行うチームが各々、せん妄への相談に対応してきました。2019年にはこの3つでチームの垣根を越えたワーキンググループを作り、病院全体でのせん妄対策づくりに着手しました。マニュアルの整備や勉強会の開催、記録方法の充実化などを行った結果、現在では入院患者全員を対象にせん妄リスクを評価し、ケアプランを立てられる仕組みが整えられました。GCNSとして、せん妄のハイリスクとなる高齢者には、個々の持つ習慣や価値観を踏まえ、環境へ働きかけることが重要だと伝えてきました。病棟ラウンドの際は積極的にスタッフと情報交換を行い、患者の言動を正しく理解できているかという視点で話し合うようにしています。
- その他にも行動制限に関するワーキンググループに参加し、講義や体験学習、事例検討などで構成されるスタッフ向けのワークショップを開催しています。担当する講義では、私たちが問題視している行動にはその人なりの意味があること、そこには加齢や疾患による機能変化、馴染んだ生活や価値観が影響していることを、丁寧に伝えるようにしています。身体拘束の実施数が減ってきたことは、こうした取り組みの成果だと考えています。
- GCNSとして何よりも、高齢者の“人としての尊厳”を守れる存在でありたいと考えています。高齢者の日常や価値観を知って関わることの大切さを、これからも伝えていきたいと思います。
- 山元 智穂
- 2007年に大学院を修了。同年社会福祉法人浴風会 浴風会病院に就職し、一般病棟、医療療養病棟、介護療養病棟(認知症対応)で勤務後入退院支援看護師として活動。2017年より現職。老人看護専門看護師の取得は2010年。
Vol.3-2
高齢者の日常や価値観を知って関わる大切さを伝えたい

- 2007年認定
国立研究開発法人 国立長寿医療研究センター
高梨早苗 - 私は、国立長寿医療研究センターの「私たちは高齢者の心と体の自立を促進し、健康長寿社会の構築に貢献します」という理念のもと、GCNSとして高齢者のフレイル予防や認知症ケア、せん妄ケア、EOLケアなどに取り組んでいます。2014年当時、認知度が低かったフレイルについて、高齢者自身や関係者がその予防に取り組めるよう、多職種で教室を開催し、栄養や運動、生活習慣、ACPについて講義やワークなどを行い、教室のテキストをホームページや学会で配信しています。また、2011年に発足したスマイルチーム―人生の最終段階における患者と家族のQOLを保つために疾患にかかわらず介入するEOLケアチーム―に2014年に加入し、活動を行っています。
- このような取り組みの中で、常に高齢者の意思や考えはどうなのかと自分に問いかけ、高齢者に聴き、想像し、ご家族、医療者、介護者といった人々と一緒に考えることを大切にしています。スマイルチームの一員として、病棟看護師や他職種と連携し、「ご本人の意思は?」という視点を中心におき、ご本人の微弱なサインの共有、苦痛症状のマネジメント、ご本人が意思表出できるような環境整備を行っています。意識変容がある高齢者に対し意識が明確な時を見計らったり、苦痛症状がある場合には最大限緩和を図り、感覚機能や認知機能低下を考慮し問いかけたりすることで意思表示が可能になることもあります。しかし、難しいときも多く、その場合、ご家族や医療者、介護者といった人々とご本人の意思を推定し「ご本人の最善のために、みんなで考えよう」といった関わりをしています。
- これらの実践・相談・調整・倫理調整といった活動を通じて、「ご本人の意思は?」と問いかける、キャッチしようと取り組む、ご家族と一緒に考える、といった医療者が少しずつ増え、さらにチームにGCNS加入後、意思決定や倫理判断に関する依頼が増えています。現在、高齢者の意思を支える力を高めるため、ラダー別の教育を取り組んでいます。
- どんな状況であっても高齢者の意思が大切にされるよう、GCNSとして支援していきたいと考えています。
- 高梨 早苗(たかなし さなえ)
- 2006年大学院修了後、西神戸医療センター(現:神戸市立西神戸医療センター)に就職し、2007年老人看護専門看護師の認定を受ける。2013年現職に就き、2018年より病院と長寿医療研修センターを兼務している。
Vol.2-1
高齢者の意思を大切にしたい
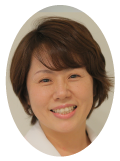
- 2011年認定
医療法人ハートフリーやすらぎ 訪問看護ステーションハートフリーやすらぎ
笹山志帆子 - 当法人は、診療所、訪問看護ステーション、居宅介護支援事業所、ナーシングデイの4つの事業があります。その中で私は、訪問看護ステーション、診療所で勤務しています。
- 診療所では、地域の方がいつでも気軽に認知症について相談できる場所を目指して、週1回もの忘れ看護外来を開いています。訪問看護では、認知症の方を担当して、認知症看護や家族支援を実践しています。
- 15年前の訪問看護では、『認知症の方に訪問看護が入る必要はあるのか?』『認知症があるので一人暮らしはできない、どこか施設に入った方がいい!』と地域の方やかかりつけ医、ケアマネジャーからの声がありました。認知症の方が住み慣れた地域で暮らし続けることができるように、認知症看護の正しい知識を得たいと考え、認知症看護認定看護師の資格取得を考えました。研修では『認知症の正しい知識』『認知症の人を中心とした考え方』が重要であることを学び、自分なりに地域で何ができるかを考えました。その結果、認知症だから一人暮らしができないと考えるのではなく、なぜ一人暮らしは難しいと思われているのかを考えるようにしました。その結果、必要である支援を見極めることで、一人暮らしが継続できるケースが増えてきました。 今では地域の方から『○○さん、今まできれいに玄関のところの花の手入れをしていたけど、最近は手入れができていないよ』などの情報をいただけるようになりました。
- 地域包括支援センター、ケアマネジャー、近医からの認知症の人への訪問看護の依頼も年々増えています。特に地域包括支援センターやケアマネジャーからは、夫と二人暮らしの方で、「毎日のように怒鳴り声が聞こえる」と近所の方から連絡が入り、虐待に繋がる可能性のある事案として訪問看護が導入される事例もあります。このような訪問看護の際には、特に本人と家族と信頼関係ができるように心がけ、同時に本人と家族の生活に関する考え方を聞き、認知症の進行状態に合わせた看護、家族支援を行うようにしています。
- 1例1例を大切に、その人の持つ力に着目し生活能力を最大限に引き出せるように、本人の意思を尊重し、その人にとって最善は何かを支援者や多職種と検討しています。今後も認知症の方、周囲の方々と話し合いながら、認知症の方が住み慣れた地域で暮らせるように認知症看護認定看護師として支援していきたいと思います。
- 笹山 志帆子(ささやま しほこ)
- 一般病院での勤務を経て、2004年医療法人ハートフリーやすらぎに入職し訪問看護を始める。2011年認知症看護認定看護師の認定を受ける。2016年日本認知症ケア学会関西2地域部会委員を受ける。2019年特定行為研修(栄養及び水分管理に係る薬剤投与関連、創傷管理関連、精神及び神経症状に係る薬剤投与関連)終了後、2019年より医療法人の理事、訪問看護ステーションと診療所の師長を兼務している。
Vol.2-2
地域で暮らす人々と共に認知症看護を実践する

- 2009年認定
公立七日市病院
齊田綾子 - 私の所属組織は回復期~慢性期医療を担う一般病院で、急性期治療を終えた患者の生活再構築支援を使命としています。私は配属病棟での看護実践活動を主体としながら他病棟でも直接的・間接的ケアを行う時間を与えられ、組織のニーズに応え高齢者・家族,スタッフのために何ができるかを問い続け活動してきました。
- 主なCNSとしての活動には退院支援があります。これは認定後2年間の実践・相談・調整・倫理調整の介入割合で退院困難事例が最多であったことや組織の使命から、優先されるCNSへの現場ニーズと捉え取り組んできたことです。取り組み当時、病棟看護師は退院支援に関心が高いものの、退院支援の流れの理解や退院後の生活を見据えたケアの見直しの必要性等のアセスメント不足があり、退院困難事例はMSWに依存傾向、院内・外の多職種間の調整が十分とは言えない状況でした。そこで、病棟看護師が主体となり退院支援を進められることを目指し、まずは病棟からCNSへの相談事例や、CNS自らが倫理調整等の必要性を判断した事例に対し、病棟看護師と共に必要な支援を検討・実践する過程を重ねていきました。特に院内・外の多職種をつなぐために多職種カンファレンスを推進しました。また退院支援チームを始動し、退院支援のフロー整備や退院支援ワークシートを作成して退院支援の全体像を可視化したり、連携施設が必要とする情報の調査結果を反映し退院サマリー項目の見直しにも取り組んできました。現在は、高齢者が安心して療養生活へ移行できるよう退院後訪問指導の運用を整備しバックアップしたり、訪問診療・訪問看護で在宅生活を支援している事例紹介の研修企画など、退院後の生活をイメージし支援できる看護師の育成に努めています。活動の成果として、多職種での退院支援の進捗の共有が積極的に行われるようになっています。
- よりよい高齢者ケアの提供に貢献できるよう、今後も努力を続けていきたいと思います。
- 齊田 綾子(さいだ あやこ)
- 1999年に富岡地域医療企業団の急性期病院に入職し、2003年より公立七日市病院で勤務。2009年にサブマネジャーとなり、同年12月老人看護専門看護師の認定を受ける。2020年4月までに、院内全病棟(障害者一般病棟,地域包括ケア病棟,回復期リハビリ病棟)での勤務を経験。2019年にマネジャーとなり病棟管理を担っている。
Vol.1-1
CNSの役割と向き合い歩んだ10年の老人看護CNS活動報告
~高齢者ケアをよりよくするため地道に歩みを進める~
~高齢者ケアをよりよくするため地道に歩みを進める~

- 2009年認定
社会医療法人蘇西厚生会 松波総合病院
住若智子 - 私は岐阜県にありますケアミックス型の病院に所属しています。当院は、ICU、HCU、一般急性期病棟、地域包括ケア病棟、回復期リハビリテーション病棟、障害者病棟を有する501床の病院で、地域の急性期から慢性期の医療を担っています。
- 主な活動は認知症ケアチーム(以下DST)の活動になります。週に2~3回、多職種チームでのラウンド・カンファレンスを行ない「認知機能の低下がある入院患者が安心できる環境で適切な治療が円滑に受けられるようにサポートする」ことを目指しています。病棟看護師の「対応の仕方がわからない」という『困った』の相談や、認知症のある方の「ニーズは何か」や「苦痛や不快な症状はないか」などを本人に『聞く』ことや『言葉の代わりに何らかのサインを発信していないか』を観察し、スタッフと一緒に考えることを大切に活動しています。また、急性期治療の場ではせん妄を併発する患者が少なくありません。そのため、入退院センターにて入院前と入院早期に「せん妄リスクアセスメント」のチェックを導入し、「せん妄ハイリスク」となった患者はDSTが早期より介入を行なっています。例えばせん妄の既往がある方に、本人とご家族から入院前の生活の様子や前回入院時の様子などを聴取し、音や光を気にされることが分かると足音や話し声に注意し、テレビの電源の光を隠すなどの環境調整をします。同時に普段使われている時計や読んでいる新聞を持ってきてもらうなど生活の継続性を大切にすることをスタッフと共有し、身体治療だけでないケアの実践することでせん妄の予防ができた事例がありました。その他の活動として、施設内には老人保健施設や訪問看護ステーションがあり法人内の認知症ケアに携わっています。法人職員や地域住民向けの「認知症サポーター養成研修」や勉強会の開催など、認知症ケアの啓発活動を行なっています。
- 認知症のある方の入院生活での混乱を最小限にし、安全で安心できる療養環境を提供し、また住み慣れた地域に戻って行けるように今後も活動を行なっていきたいと思います。
- 住若 智子(すみわか ともこ)
- 看護師免許取得後、地域に根付いた民間の病院に入職し、循環器病棟・内科一般病棟に勤務。2009年に認知症看護認定看護師の資格取得後、療養型病棟、地域包括ケア病棟での勤務を経験し、退院調整や地域との繋がりを学ぶ。2017年から現法人に入職し、法人内の認知症ケアに携わっている。
Vol.1-2
認知症のある方の入院生活を支えるチームアプローチ


