-
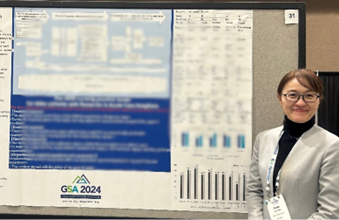
今回,参加した学会は,The Gerontological society of America (GSA)Annual scientific meeting 2024です.11月13日から4日間参加し,ポスター発表とショートプレゼンテーションをしました.GSAは,老年学分野で研究,教育,実践に取り組んでいる最古かつ最大の学際組織です.1945年に設立され,50か国以上の様々な分野の学際的なコラボレーションを促進しています.毎年4,000人あまりの専門家を年次集会に集め,毎年500を超えるセッションが開催され,あらゆるレベルのキャリアの専門的な「拠点」を提供しています.
まず,学術集会に参加して圧倒されたのは,その膨大なセッションの数と多様性とホスピタリティです.関心領域はもちろんですが,AI開発や,政策など様々な分野のセッションに触れることで,考えてもみなかった観点からのアイデアが浮かんできたりもしました.また,音楽やヨガのイベント等も開催され,それらに参加するのも楽しかったです.開催前に学会会員になると,様々なワーキングループから関心領域のグループへオンラインで参加することができ,当日対面でお会いして情報交換をし,ネットワークを作ることもできました.そして,アメリカ本国以外にも,アジア,アフリカ,ヨーロッパの国々からの参加者とお話をする機会があり,世界は広い,けれども,近いものだと感じさせられました.
私は博士研究の一部をポスター発表し,今回はショートプレゼンテーションの座長の役割も経験することができました.発表内容は急性期病院の認知症高齢者のShared decision-making(SDM)看護実践モデルの開発についてでした.急性期病院の臨床において,認知症高齢者の医療についての最善の選択をするための支援について,多職種協働のSDMのプロセスとそこに位置づく看護実践をモデルとして示したものです.発表について関心を持った参加者から,急性期医療の現場の時間的制約による支援の難しさやスタッフへのトレーニングの必要性などの意見交換ができました.それによって日本が高齢先進国であり,高齢者についての概念を改めて捉えなおし,世界各国へ発信していくことが必要なのだと感じました.本研究の重要性や,公表の必要性について意見を頂き,今後の研究へ取り組む意義を再確認することができました.
私は,老人看護専門看護師としても実践で活動しています.超高齢社会において,人々が幸せに年老いていく社会のために何ができるかについて学会で様々な見識に触れ,専門看護師のネットワークはもちろん,学際的な研究者とともに考え,取り組んでいきたいと考えるようになりました.そのために,GSAは,最適な「拠点」であり,学会員間でのコラボレーションを促進できる場を提供してくれると考えています.英語は得意ではありませんが,コツコツ勉強しています.今後もコンスタントに学会に参加し,ネットワークを広げていくつもりです.
GSA2024参加報告
日本医科大学千葉北総病院 老人看護専門看護師 齋藤多恵子
-
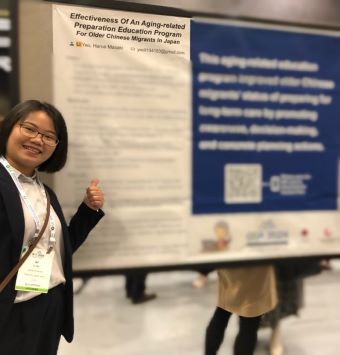
2024年11月にアメリカのシアトルで開催されたGerontological Society of America 2024 Annual Scientific Meeting (GSA2024) に参加しました.GSAはエイジング分野における研究,教育,実践に関する,アメリカで最も大きな学際的組織です.今回の学術集会では約4000件の演題が発表され,40カ国以上から参加者が集まりました.
「The Second Fifty Answers to the 7 Big Questions of Midlife and Beyond」を執筆した著者との対談講演では,アメリカにおける老いの社会的現状やその対策について議論が交わされ,海外の現状を踏まえたうえで,自分の博士研究の考察に役立つヒントを得ました.また,「My Journey in Gerontological Research」をテーマにしたMaxwell A. Pollack Award for Contributions to Healthy Agingの受賞者講演では,受賞者が数十年にわたって行ったoral healthとhealthy agingに関する研究の軌跡が紹介されました.この講演を通じて,oral healthの重要性を再認識し,講演後には受賞者との対話を通じて,自分の研究者キャリアに役立つ貴重な意見を得ることができました.
今回,博士研究成果の一部を「Effectiveness Of An Aging-related Preparation Education Program For Older Chinese Migrants In Japan」(Li Yao; Harue Masaki)をテーマにポスター発表しました.本研究は,日本に在住する中国人高齢者を対象に,要介護生活に焦点を当てた老いへの準備教育プログラムの介入前後および追跡調査の結果を分析し,発表しました.会場では,心理学専門の参加者と今後の研究に向けた研究デザインについて意見を交換しました.また,アメリカに住む中国人研究者からは,自分の将来の要介護生活について心配を抱えながら,本研究に興味を持って議論しました.
この演題についてflash poster session でoral presentationを行い,Academy for Gerontology in Higher Education Student Stipendを受賞しました.今回の学会参加では,英語で発表することに少し緊張しましたが,今後,国際的な舞台で自分の研究成果を発信する意欲や自信がさらに湧いてきました.
GSA2024参加報告
千葉大学大学院看護学研究院 姚 利
-
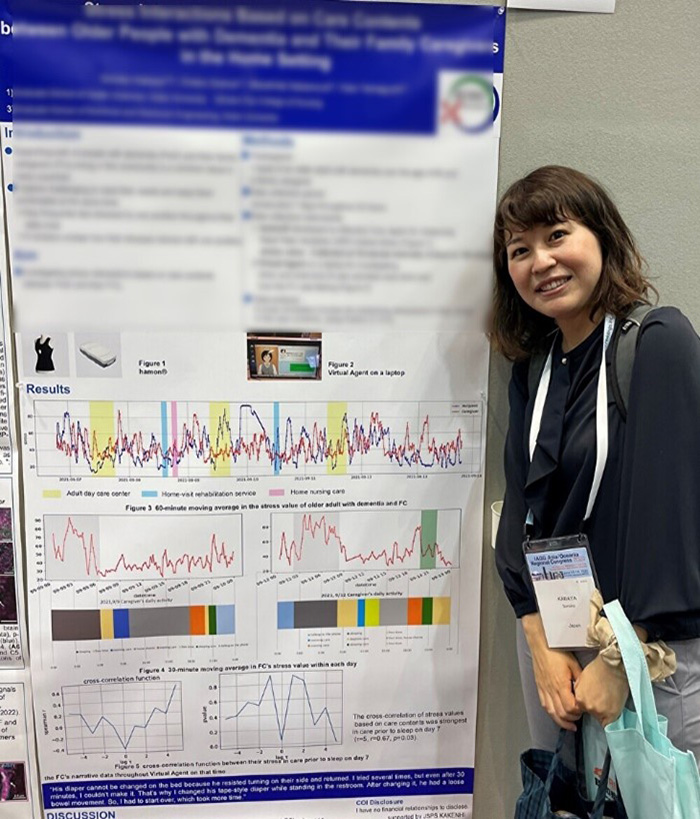
私は,2023年6月12日から14日の3日間,神奈川県のパシフィコ横浜で開催された12th International Association of Gerontology and Geriatrics Asia/Oceania Regional Congress2023に参加しました.IAGGは世界65か国以上に73の会員組織があり,医療や行政などの様々な専門家で構成されている老年学を推進する学際的かつ国際的な組織です.
仕事の関係で12日のみの参加となりましたが,ICTやAI等を活用することで,高齢者の豊かな生活に寄与できるような研究活動を実施していきたいと考えており,特にGerontechnologyのシンポジウムを楽しみに参加しました.シンポジウムのなかでは,海外の介護施設でのロボット技術を活用したケアの取り組みや,客観的データと主観的データを統合した包括的なアセスメントツールの国際的な共同開発など,様々な先駆的な取り組みが紹介されていました.高齢者の生活を支えるテクノロジーは日々進化しており,それらを基に他分野と協働しながら,それぞれの高齢者に合わせたケア方法の開発を行っていきたいという思いがより強くなりました.
私は,現在博士後期課程で,先生方と共同で取り組んでいる研究の一部をポスターで発表しました「Stress Interactions Based on Care Contents between Older People with Dementia and Their Family Caregivers in the Home Setting」(Sonoko Kabaya,Chieko Greiner,Masahide Nakamura,Yuko Yamaguchi).認知症高齢者とその家族介護者は日々の生活のなかで様々な場面でストレスを感じながら生活をおくられています.今回は特にケア場面に注目して,そのなかでの両者の感じるストレスがどのように相互に作用しているのかを分析しました.関心を持ってポスターの前で立ち止まってくださった方と英語でディスカッションをする機会は,とても有意義で,更に研究を発展させていくための多くの示唆を得ることができました.
国際学会に参加したなかで,対面で自身の研究内容について発表した経験は今回が初めてでした.まだまだ未熟ではありますが,超高齢社会を経験している日本の研究者として,国際的な場で研究活動や日本の老年看護の知見を発信し,共有していくことを大切にこれからもがんばっていきたいと思います.
IAGG活動報告
神戸市立看護大学 蒲谷苑子
-
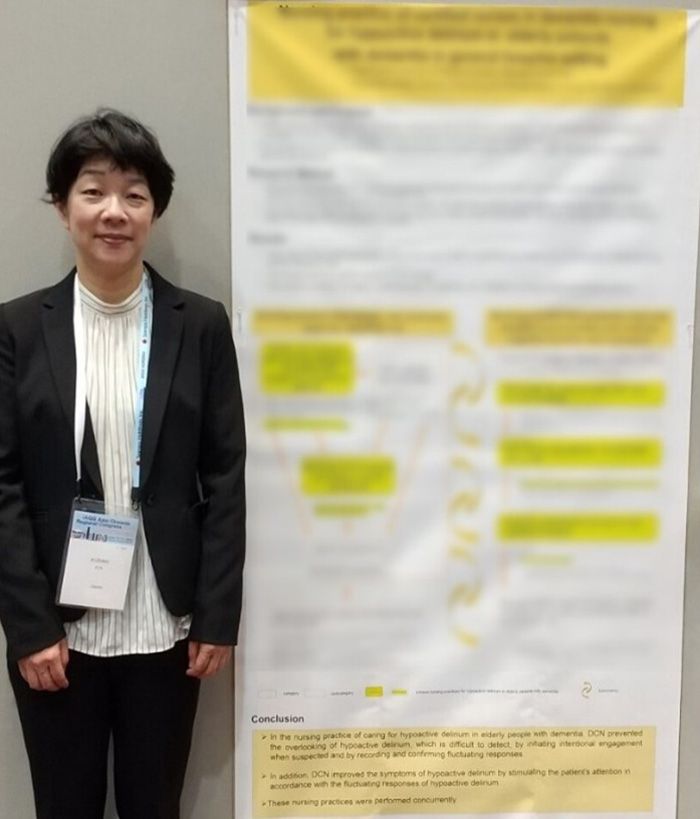
2023年6月に横浜で行われたThe International Association of Gerontology and Geriatrics Asia/ Oceania Congress 2023に参加しました.国際学会へ初めて参加し,医学,看護学,社会科学など様々な分野からの研究発表や講演の触れる ことで,アジア・オセアニア地域の高齢化における課題やその取り組みについて知ることができ,視野が広がりました.
会場ではフレイル,サルコペニアに関連する高齢者の生活上の問題についての講演や発表が多くありました.中 でも印象的であったのが,日本でも多くの高齢者に行われている股関節骨折への治療とその後についての諸外国との違 いでした.日本では手術後,骨折前の生活を目指して治療が行われています.しかし,アジア地域の国々の中には医療制 度や治療に対する考え方の違いにより,ケアの連携不足から手術1年後の生存率が低く,5人中3人は骨折前の運動可能な 状態に回復できない状況にあるとのことでした.高齢化が進む中,股関節骨折のみならず脆弱性骨折へのケアは,高齢者 がその人の望む生活を維持するためには欠かせない課題であると再認識しました.
今回,修士論文でまとめた認知症高齢者の低活動型せん妄への認知症看護認定看護師の看護実践についてのポ スター発表をする機会を得ました.演題名は 「Nursing practice of certified nurses in dementia nursing for hypoactive delirium in elderly patients with dementia in general hospital setting」です.せん妄のサブタイプの中で低活動型せん妄は認知症やうつなどと判断がつきにくく,認知症高齢者が低 活動型せん妄を発症した場合は,さらに見逃され介入につながりにくいとされています.発表内容については,そもそも 低活動型せん妄がどのようなものであるか,認知症看護認定看護師ならではの看護実践がどのようのものであったのか についてのご質問をいただきました.また,臨床では低活動型せん妄を発症が疑われる認知症高齢者が介入されずにい ることが多くあるとのご意見もいただきました.認知症高齢者の低活動型せん妄への看護実践については,さらに研究 を進めていく必要があることを感じました.
今回国際学会に参加して,高齢化における課題は認知症,フレイル,慢性的な疾患の管理など多岐にわたっている ため,様々な分野の研究が参集し繋がることの意義を実感しました.障害や疾患とともに生きる高齢者とその家族がよ りよく生きる生活をささえることができるように,看護の立場から情報を発信できるように努めていきたいと思いまし た.
